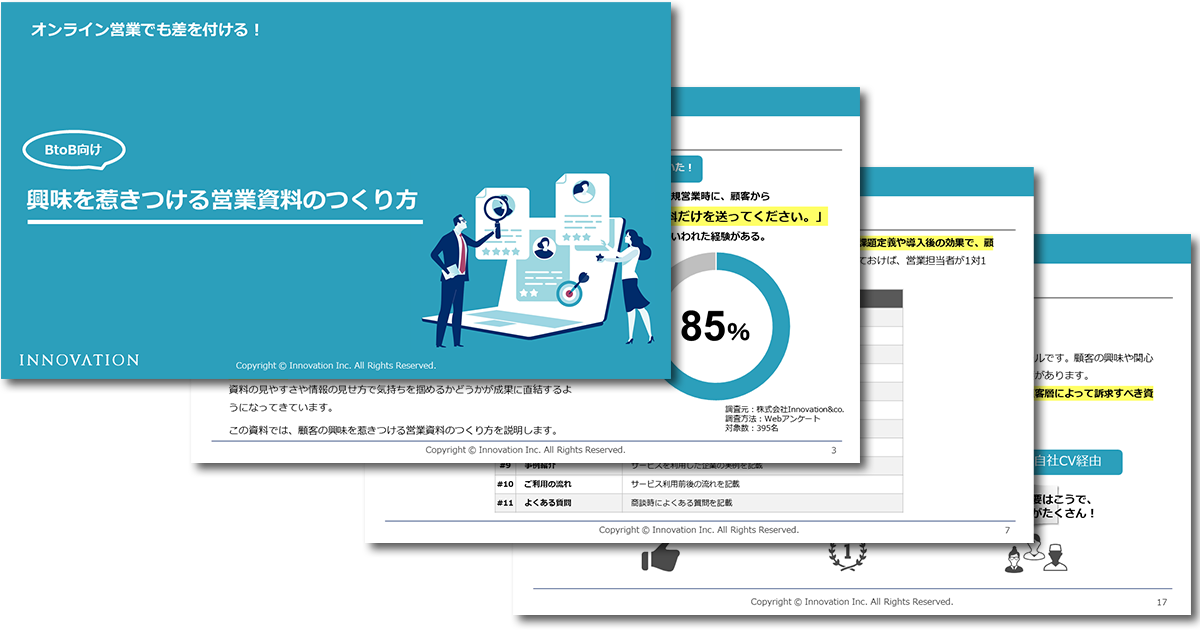キーマンを見極める!BtoB営業で成果を上げるアプローチ方法とは?

BtoB営業で成果が出ない原因の一つに「話すべき相手を間違えている」ことがあります。どれだけ良い提案でも、決裁権を持たない相手に届けていては、商談は前に進みません。「誰に」「どのように」アプローチすればよいかが明確になれば、商談の進行スピードも成約率も一気に改善されるはずです。
この記事では、BtoB営業において成果を大きく左右する「キーマン(=決裁者)」の見極め方と、的確にアプローチするための実践的な手法を徹底解説します。
- ▼この記事でわかること
- ・キーマンの定義と役割
- ・キーマンを見極める3つの実践的な方法
- ・キーマンに効果的にアプローチするための具体的な手段
キーマンとは?営業活動における重要人物
営業活動における「キーマン」とは、最終的な購買・導入の意思決定を行う人物、すなわち「決裁者」を指します。法人営業においては、製品やサービスの導入に関して、現場の担当者だけでは決定権がなく、最終的にはこのキーマン=決裁者の承認が必要となります。
企業によっては決裁権限が段階的に設定されており、数十万円レベルであれば部門長、数百万円規模であれば役員や社長がキーマンとなるケースもあります。営業担当者は、こうした社内の意思決定フローを早い段階で把握し、キーマンに直接アプローチする必要があります。
キーマンとの接点を持てるかどうかは、商談の進行スピードや成約率に大きな影響を与えます。どれだけ担当者の理解を得たとしても、キーマンの承認が得られなければ商談は止まってしまうからです。
法人営業ではなぜキーマンアプローチが重要なのか?法人営業の特徴
ここでは、なぜ法人営業ではキーマンアプローチが必要なのか、法人営業の特徴から考えていきましょう。
BtoBビジネスでは担当者の「Yes」だけでは受注にならない
法人企業が自社に製品・サービスを導入するには、担当者個人の意思だけで決定することはほぼありません。多くの場合、事業部決裁、役員決裁、社長決裁など、最終的には決裁者、いわゆるキーマンの了承を得る必要があります。
したがって、より成果を上げていく為には、最終ゴールである決裁者(=キーマン)にいかに多く接触し、製品・サービスの魅力を伝える商談をどれだけ増やせるかが重要な鍵となるのです。
みなさんもトップダウンで受注が決まった、あるいは失注したという経験はあるかと思います。法人営業において「誰と商談をするか」は、非常に重要な要素と言えます。売れる営業はキーマンとの商談率も非常に高いといっても過言ではありません。
商談がスムーズに進むかはテレアポの段階で決まっている
テレアポをする多くの営業は、企業リストの作成後すぐにテレアポをしてしまいがちで、キーマンアプローチを徹底できていないのが現状です。
運よくキーマンに接触できる場合もあるかもしれませんが、それではなかなか安定した成果(案件化率や成約率)を出すことは出来ません。これは数字を追いかける営業にとっては致命的な問題です。
また、間違った方にアプローチをすると、受注までかなり長い道のりを歩くこともあります。「一度お会いしたご担当者様が窓口になってしまい中々キーマンと会えない...」こんな経験はないでしょうか?
法人営業はただでさえ受注期間が長いことが多いため、これも営業にとっては問題です。これらの問題を解決するためには、商談の機会を創出するテレアポの時点から「誰にアポイントをとるか」を徹底的にこだわって望む必要があります。
なぜキーマンアプローチはアポ率を高めるのか?
キーマンアプローチを徹底したリストが成約率の高いリストになるのは想像のとおりですが、実は、「アポ率の高い営業リスト」になるということもあります。
理由は、現場担当者は日々の業務や数字に追われ、中々新しいことを検討する時間がありませんが、キーマンは往々にして効率化やコストカット、次の戦略を考えており、いつでも情報収集する態勢ができているからです。
それでは、どうやってキーマンを探すのか?キーマンの探し方は、自社の製品・サービスの決裁者となる方がどのような部署の方で、どのような役職の方が多いのか、過去の受注経緯から分析することから始まります。
実践!キーマンはこうやって探す!キーマンを見極める3つの方法
ここでは、営業活動の成果を左右する「キーマン」を見極めるための具体的な3つの方法をご紹介します。
①商談中のトークで確認する
キーマンを見つけ出すうえで、最も確実で実践的な方法のひとつが、商談中のトークから情報を引き出すことです。商談の初期段階では、相手がキーマンかどうかは名刺や役職名だけでは判断できないことが多く、ヒアリング力が営業担当者の腕の見せどころとなります。
たとえば以下のような質問は、キーマンかどうかを見極める手がかりになります。
- ・「こちらの件について、最終的な意思決定はどなたがされますか?」
- ・「過去に類似商品を導入された際は、どのような意思決定プロセスでしたか?」
こうした質問を自然な会話の流れの中で差し込むことによって、相手の役割や立場を把握することができます。
②自社サービスの特性から、キーマン像を考える
法人営業において「キーマン」とは、製品・サービスの導入を決定する人、すなわち決定権者のことを指します。また、多くの場合決定権者と予算を執行する「決裁者」は同一であるため、法人営業ではキーマンと決裁者はほぼ同一の意味で使われています。
それでは、ここで言うキーマンとはいったいどんな方か。まずは自社の製品・サービスの検討者がどのような部署の方かを分析する必要があります。人材系のサービスであれば人事部の部長、セキュリティシステムであれば情報システム部の部長、アクセス解析ツールであればマーケティング部の部長、大雑把に言うとこんな具合です。
「そんなの分かってるよ!」と思われた方、仰る通りです。ここまではどんな営業でも当然把握していることと思います。しかし重要なのはここからです。
③企業規模や組織構成からキーマンを見極める
結論から言うと、企業の"規模"、"組織構成"、"歴史"によって、キーマンがいる部署や役職は異なってきます。たとえば、「社員数500名の上場企業」と「社員数50名の中小企業」にそれぞれ人材サービスを営業する場合、キーマンはどちらとも人事部の部長でしょうか?
おそらく前者は人事部の部長が、後者は社長が、それぞれキーマンになると思います。従業員が多い企業では部署単位で権限移譲されている場合が多く、従業員が少ない企業であればトップダウンの風土が強くなるのがその理由です。
キーマンを分析する際は部署や役職だけではなく、企業ごとに分析をする必要があります。分析方法としては過去の成約事例をもとに、「どの部署」「どの役職」の方がキーマンだったかを調べることです。そのうえで、企業規模や組織構成、歴史といった情報を加味し、分析していくことが重要です。
以下では、特に気をつけてチェックをするポイントをご紹介します。ただし、製品・サービスによっては当てはまらないこともあると思いますので、あくまでひとつの参考としてご覧下さい。
- 企業規模
- ・従業員数200名をひとつの基準とする(200名を境に最終決裁者が社長でなくなるケースが多い)
- ・200名以上は役員or事業部長 / 200名以下は社長にアタック
- 組織構成について
- ・組織図の有無をチェック
- ・対象部署は社長直下かそうでないか
- ・検討に関わってきそうな部署は他にあるか
- ・会社概要で役員が複数人存在するか(複数人存在する場合いずれかが決裁者である可能性が高い)
- 歴史について
- ・一族経営かどうか(一族経営の場合、社長or同じ名字の方がキーマンの可能性が高い)
キーマンと接点を持つためのアプローチ方法
せっかく良い提案を行っても、キーマンに情報が届かなければ商談は進展しません。ここでは、キーマンと接点を持つための実践的なアプローチ方法を2つ紹介します。
①商談時にキーマンの同席を依頼する
最もシンプルかつ確実な方法が、初回または次回商談においてキーマンの同席を依頼することです。現場担当者との商談中に以下のような一言を添えることで、自然な形でキーマンとの接点を作ることが可能です。
「次回は決裁権をお持ちの方に同席いただけると、より具体的なお話ができるかと思います。」
このように伝えることで、キーマンの同席をお願いする理由が明確になり、無理なくキーマンとの接点を築くことができます。
②展示会・セミナーで得た情報を活用してアプローチする
展示会やセミナーに参加した際は、キーマンと直接話せる貴重な機会となります。名刺交換した相手が役職者や意思決定層であれば、その接点を起点に営業アプローチを仕掛けましょう。
また、参加者リストや登壇者情報などをもとにキーマンにアプローチすることで、事前リサーチの丁寧さや営業の本気度が伝わり、相手との信頼構築につながる可能性があります。
キーマン選定の注意点!担当者の上司がキーマンであるとは限らない
法人営業においてよくある誤解のひとつが、「担当者の上司=キーマン」という思い込みです。確かに上司であれば一定の影響力はありますが、実際の決裁権を持っている人物が別部署にいるケースや、さらに上層部に位置していることも多くあります。
たとえば、現場の担当者が営業部門に所属していても、最終的な導入判断は経営企画部や役員会でなされることもあります。組織構成や意思決定プロセスは企業によって異なるため、「誰が意思決定に関与しているのか」を丁寧に見極めることが、キーマンアプローチ成功の鍵となります。
最後に
この記事でご紹介した内容は、2〜3年目の営業であれば理解している方は多いと思いますが、属人化していてチームのナレッジになっていないことが多々見受けられます。
事業の数字がトップ営業に依存してしまっている組織はその分リスクも高くなるので、是非チームメンバーでシェアをし合い、チームの共通認識に変えていくことも併せて徹底していきましょう。
これを読んでもっとUrumo!
この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。