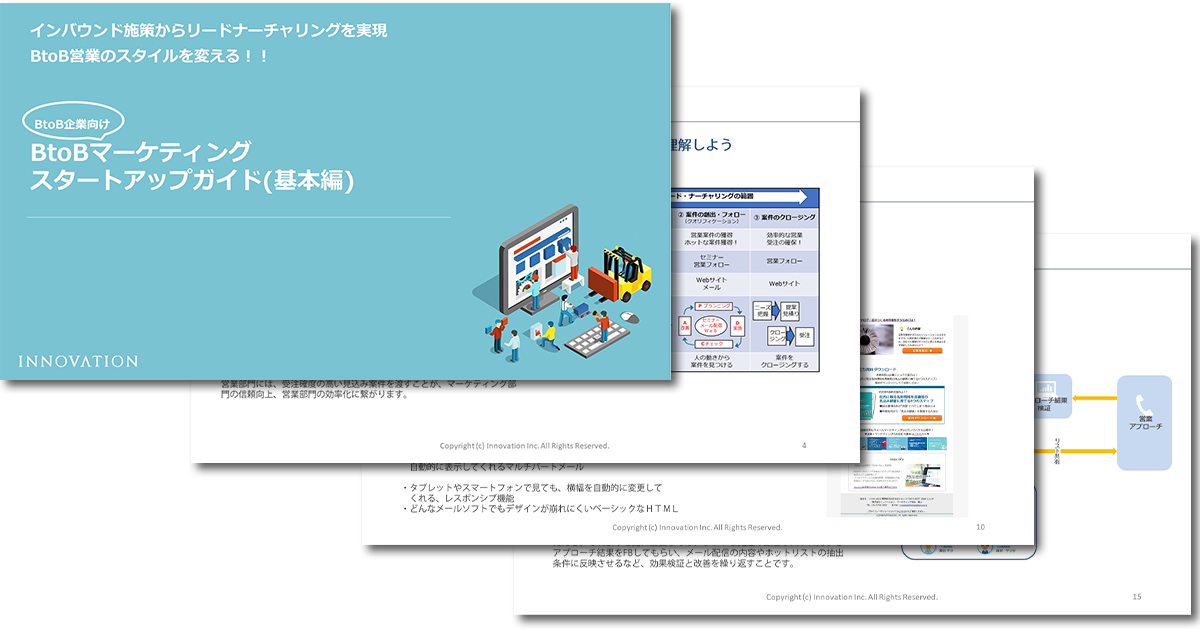企画力とは?高め方やインプット・アウトプットのコツを解説

企画力とは、隠れた課題を見つけ出し解決方法や実行までの道筋を立案する力のことです。企画力を磨くためには、日々の生活や仕事中のインプット・アウトプットの「質」と「量」が大切です。
マーケティングの仕事をしていると、「なにかいい企画はないか?」や「このアイデアを企画としてまとめてくれ」など、「企画」という言葉にふれる場面は多くあります。しかし初めて聞いた人は「いきなり企画なんて言われても・・・。」と考え込んでしまうことも多いのではないでしょうか。
実は、企画力はマーケティング業務において非常に重要な能力なのです。では、どうすれば身につけられるのか?この記事ではそもそもの「企画」の意味から、良い企画を生み出すために押さえるべきポイントについてご紹介します。
- ▼この記事でわかること
- ・企画力とは?
- ・企画力がある人の特徴
- ・企画力を高める方法
- ・企画を構成するのに必要なスキル
「企画する」って、どんな意味?
みなさんは、何気なく先輩社員が使っている「企画(する)」の意味、正しく理解できていますか?まずはその意味から考えていきましょう。
企画=斬新なアイデアではない?
企画と聞くと、ゼロからなにかを生み出す斬新なアイデアと思う人もいるかも知れませんが、それは「企画」ではなく、単なるアイデアに過ぎません。
企画とは、「なにかを実行するために、その目的や内容、実行までの道筋を示したもの」と考えれば良いでしょう。
企画とは、現状の課題を解決するために人を動かすもの
なにかを実行したいと思った裏側には、おそらくそう思った背景があるはずです。現状に何かしらの課題や不満があり、それを解決するためのものが企画なのです。
ただし、その解決手段が自分ひとりで実行できるのであれば、わざわざ企画を作る必要はありません。自分一人では解決できず、誰かを巻き込む必要がある際に「企画」となります。人を動かすには、それなりの根拠やその企画を実行したあとの姿、実現までの方向性・道筋などが必要になってきます。
「良い企画を生み出す力」=「企画力」とは?
企画とはどういうものかがわかっても、いきなり良い企画を作るのは難しいかもしれません。多くの人を動かすような、魅力的な企画を作るには、それを生み出す力=「企画力」が重要になります。それではこの「企画力」とはいったいどのような力なのか、整理していきましょう。
【日常に潜む課題や不満に気づく力】現状に対する課題や不満は、いたるところにある
先ほど、「企画は現状の課題を解決するために作るもの」と説明しましたが、現状に特に不満や課題を感じていないため、企画を作るのが難しいと感じる方もいるのではないでしょうか。
もしかしたら、世の中の不便や課題に対して「こういうものだ」と思い込み、我慢してしまっている可能性もあります。現状に対する課題や不満は、そのすべてが顕在化しているわけではありません。その多くは、無意識のうちにその不自由を受け入れてしまっているのです。
たとえばSONYのウォークマンを例に考えてみましょう。それまで、「音楽は持ち歩くものではない」という認識が一般的でした。しかし、潜在的な不満として、「どこでも自由に音楽を楽しみたい」という不満があったからこそ、ウォークマンがここまでヒットしたのでしょう。
「〇〇なんだから仕方がない」「〇〇して当然」そんな言葉の裏に、課題や不満が隠れていることが多くあるのです。
【隠れた課題を見つけ出す力】課題発見こそが企画力の本質
こういった隠れた不満や課題を見つけ出すことができれば、それに対する解決策を模索し、導き出すこともできるはずです。その導き出された解決策が、「企画」になるのです。
つまり「企画力」とは、日常に潜んでいる「当たり前」の裏に隠されている課題をいかに見つけ出すことができるか、ということであるといっても過言ではありません。
企画力と提案力の違いとは?
「企画力」と「提案力」は似ているようで、役割やプロセスが異なるスキルです。企画力は、まだ言語化されていない課題やニーズを発見し、それに対してどのようにアプローチすべきかを構想・設計する力です。
問題の本質を見抜き、目的に沿った解決策をゼロから考え出すことが求められます。いわば、アイデアを「生み出す」力です。
一方で提案力は、すでにある企画やアイデアを相手に「伝え、理解・共感してもらう」ための力です。論理的な説明やプレゼンテーション、相手の状況に合わせた言い回しや資料の工夫など、受け手に応じた表現力が問われます。
つまり、企画力が「0から1を生み出す力」であり、提案力は「1を10にして届ける力」といえるでしょう。どちらもビジネスには欠かせませんが、起点となるのは課題発見と構想を担う企画力です。
企画力がある人の4つの特徴
「企画力がある」と評価される人には、どのような共通点があるのでしょうか。ここでは、4つの特徴を具体的に紹介します。
1.好奇心や探求心がある
企画力がある人は、常に多様な情報にアンテナを張り、自分の視野を広げ続けています。日々のニュース、業界のトレンド、SNSでの声、書籍など、幅広い情報源から知識を吸収し、「今、何が求められているのか」「何が課題になりうるのか」といった洞察力を養っています。
これにより、自分の興味の範囲にとどまらない客観的な視点で企画を立てることができ、社会や顧客の変化にも柔軟に対応できるのです。インプットの量と質が、企画の質を左右すると言っても過言ではありません。
2.洞察力がある
優れた企画力を持つ人は、物事の表面ではなく、その奥にある「本当の問題」を捉える力に長けています。目に見える現象の裏にある背景や原因に着目し、誰の、どんなニーズに応えようとしているのかを明確にします。
表面的なアイデアに飛びつくのではなく、ユーザーや社会の課題に寄り添い、それに対して最適なアプローチを探る姿勢があるため、実現性の高い、納得感のある企画を立てることができます。
3.相手に伝える力がある
どんなに良いアイデアも、関係者に伝わらなければ企画として成立しません。企画力がある人は、自分の考えを筋道立てて整理し、相手が理解しやすい言葉でわかりやすく伝える力を持っています。
背景・課題・目的・手段・成果といった構成を意識しながら説明することで、企画への納得度を高めることができます。また、相手の立場や関心に応じて伝え方を変えられる柔軟性も、周囲の理解を得るうえで重要です。
4.計画力と行動力がある
企画力は構想だけで完結するものではありません。実際に形にし、成果につなげてこそ評価されます。企画力がある人は、理想論だけではなく「実現可能性」を見据え、必要なリソースやステップ、スケジュールを具体的に計画できます。
さらに、自ら動き、関係者を巻き込みながら着実に実行していく行動力も兼ね備えています。課題を整理し、論理的に組み立て、実行可能な形に落とし込むことが、現場で「使える」企画力なのです。
「企画力」を磨くには?
それでは、この「企画力」、どのようにして磨いていけばよいのでしょうか。
1.インプットの「質」と「量」を増やす
まず重要なのは、インプット(情報収集)の量と質です。多くの人と触れ合ったり、読書をして知識を吸収したりすることで、自分がこれまで経験したことのない新たな刺激を多く受けられます。
その中には、一見当たり前のこととして受け入れられていても、実は改善できる点が多くあるはずです。そのようなところに、企画の種が眠っていることが多いのです。また、過去に作られた企画を確認しなおすことも重要です。過去の情報は、自分が企画をする上での参考事例になり、新たな企画を考える手助けになるでしょう。
マーケティングの場面で考えると、ユーザー調査とその分析をはじめ、営業担当が直接顧客や販売元などから収集したニーズ、競合商品の調査、過去に発売した商品のレビューや口コミなどが、企画を考える上での良いインプットになります。ユーザーのニーズを深堀りする際は、「定量」「定性」の両面から調査することが重要ですが、それぞれ適した調査手法は異なります。
定量的な調査に有効な手法としては、「アンケート調査」が挙げられます。数値から状況を客観的に判断できるため、企画の根拠を明らかにすることができます。また、選択肢式の設問を用意することで、ざっくりとした課題の方向性を把握することも可能になります。
定性的な調査には、「ユーザーへの訪問」や「グループインタビュー」などが適しています。ユーザーが自由に発言する生の声から、定量調査だけではつかみにくい温度感や細かな不満などが浮き彫りになり、具体的な課題の把握、整理に役立てることができるでしょう。
2.小さなアウトプットを積み重ねる
ただ知識を得るだけでは、収集した情報を活用しきることは難しいでしょう。インプットするだけではなく、実際に何度も企画をして経験を積み、応用力を高めることも重要です。そのために、普段から細かくアウトプットする習慣をつけることが効果的です。
たとえば、身の回りのアクシデントについて、なぜその事象が起きたのかを深掘り、その原因や再発防止策を自分なりに考えてメモしたり、街中で見かけるキャッチコピーに心ひかれた理由を考えてみたり、といったことを繰り返すことで、収集した情報を自分の中で整理して、誰かにわかりやすく伝えるための訓練になります。
また、身の回りにあるものを分析する習慣をつけることで、企画のまとめ方や人に伝えられるために必要な視点などが身につくことにもつながるでしょう。
3. フレームワークで思考を整理する
企画を立てる際には、情報を論理的に整理する技術も重要です。そのために役立つのが、マーケティングや課題解決で使われるフレームワークです。たとえば「3C分析」「4P分析」「SWOT分析」などを活用することで、思考を抜け漏れなく構造化できます。
また、全体を漏れなく分類する「MECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)」の考え方を身につけると、複雑な情報をシンプルに分類でき、企画書の説得力も高まります。こうしたフレームを習慣的に使うことで、企画力に必要な論理性が自然と磨かれていきます。
- 3C:
- Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)、(+Channel(チャネル))
- 4C:
- Customer value(顧客価値)、Customer cost(顧客コスト)、Convenience(利便性)、Communication(コミュニケーション)
- 4P:
- Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(プロモーション)
- SWOT分析:
- 強み(Strengths)、弱み (Weaknesses)、機会 (Opportunities)、脅威 (Threats)
企画力を支える4つの基本スキル
ここでは、企画を構想し、形にし、周囲を動かすうえで不可欠な4つのスキルを紹介します。
リサーチ能力
企画の出発点は「情報」です。適切なリサーチができる人は、ユーザーのニーズや市場の動向、競合の施策などを多角的に把握し、企画の方向性を確かな根拠で支えることができます。
表面的な情報だけに頼るのではなく、仮説を立てながら必要なデータを収集・分析することで、企画にリアリティと説得力が加わります。SNSやレビュー、統計データ、ユーザーインタビューなど、複数の手段を使い分けて情報を集める力が求められます。
ロジカルシンキング
論理的思考力(ロジカルシンキング)は、バラバラの情報やアイデアを筋道立てて整理し、納得感のある企画にまとめ上げるための核となるスキルです。
課題の原因と解決策の因果関係を明確にし、誰にでも理解できる構造でアイデアを組み立てることで、説得力ある企画が生まれます。MECEやフレームワークを活用し、漏れやダブりを防ぎながら思考を整理できる人は、企画の質も自然と高まります。
コミュニケーション力
企画は一人で完結するものではありません。実現には、上司・クライアント・メンバーなど多くの関係者との協力が必要です。そこで重要になるのが、相手の立場を理解し、円滑に意思疎通を図る「コミュニケーション力」です。
対話を通じて相手のニーズを引き出したり、フィードバックを受け入れて企画を改善したりする柔軟性も含まれます。信頼関係を築く力こそ、企画の実行力を高める鍵となります。
プレゼンテーション能力
どれほど優れた企画であっても、相手に正しく伝わらなければ意味がありません。プレゼンテーション能力は、企画の価値をわかりやすく、魅力的に伝える力です。話の構成、スライドの見せ方、言葉選び、表情や声のトーンまでを工夫し、聞き手に共感や納得を与えることが求められます。
また、相手の関心や背景に合わせて伝え方を変えるスキルも重要です。プレゼン力の高さは、企画の採用率にも大きく影響します。
まとめ
いかがでしたか?企画とは、斬新なアイディアを出すことではなく、現状の課題を解決するために作るものであるとご紹介しました。本記事を参考にしていただき、ぜひみなさんも企画力を磨くためにインプットとアウトプットを意識して行ってみてはいかがでしょうか。
これを読んでもっとUrumo!
この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。