マーケティングオートメーション導入の流れ・注意点は?
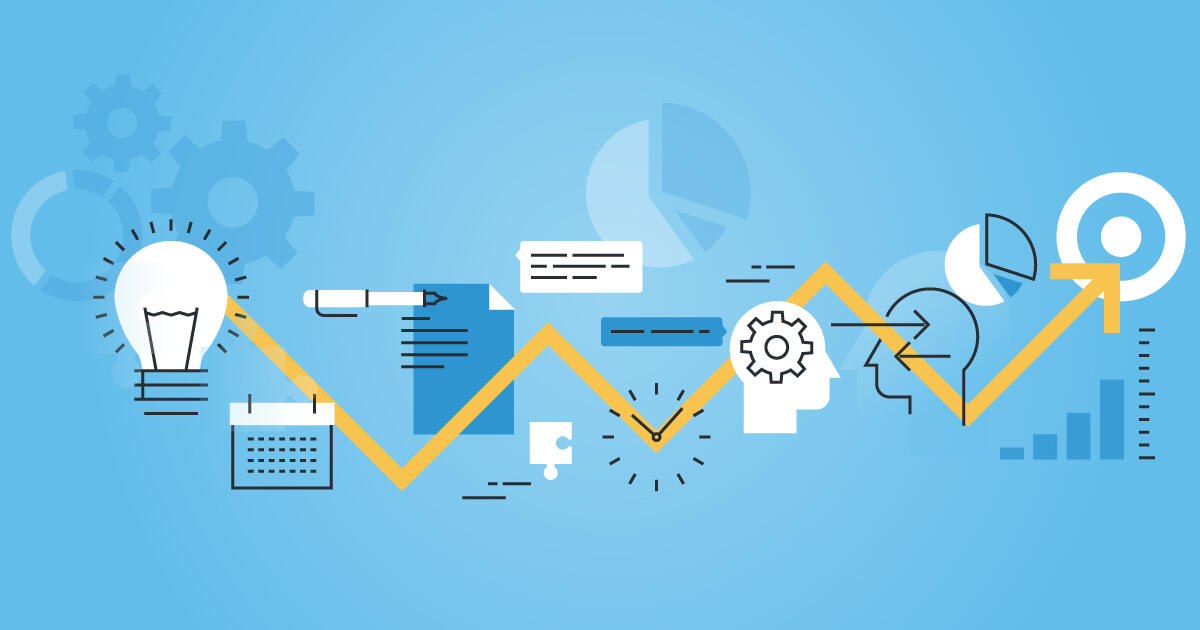
「マーケティングオートメーション」というツールが2014年ごろから日本でも広がりを見せています。
2017年に株式会社ジャストシステムが行った調査によると、日本企業でマーケティング担当がいる会社の17%がマーケティングオートメーションを導入しているとのことです。
徐々に導入率が上がってきているマーケティングオートメーションですが、名前は知っているが詳しくは知らない、という企業担当者が多いというのも現状です。そこでこの記事では、マーケティングオートメーションの導入の流れと注意点についてお伝えします。
また、「マーケティングオートメーションについて、1から教えてほしい!」という方向けに、「マーケティングオートメーションの教科書」を作りました。ぜひ、こちらからダウンロードしてください。
マーケティングオートメーションとは
まず、マーケティングオートメーションとはどのようなものなのかを理解しておきましょう。
マーケティングオートメーションとは、一言でまとめると「マーケティング業務を効率化・自動化できるツール」のことです。
マーケティングの業務は、見込み顧客を管理し、動きを見定めて適切なタイミング・内容のアプローチをすることで、売上を伸ばす手助けをすることです。そのため業務の内容が非常に多岐にわたり、さらに顧客数が多いととても管理しきれないという問題点がありました。
さらに、大量消費・大量生産の時代が終わり、物やサービスが溢れている現代では顧客のニーズが多様化しています。そのニーズに対応するには顧客の動きを検知して確度が高いタイミングで営業をかける必要があります。
このような、業務の自動化や顧客の動きをチェックするためのツールがマーケティングオートメーションなのです。
マーケティングオートメーションを導入することで、見込み顧客の管理体制が整い、見落としていたホットリードや、休眠顧客の抽出も簡単にできます。
マーケティングオートメーション導入の流れ
では次に、マーケティングオートメーションを導入する際の流れについて見てみましょう。実際にはこのような流れを踏む必要があります。
- 1.課題のピックアップ
- 2.導入するツール選び
- 3.カスタマージャーニーの構築
- 4.社内の役割分担の検討
- 5.他部署との連携
1.課題のピックアップ
マーケティングオートメーションを導入するときには、まず現状抱えている課題をピックアップする必要があります。
マーケティングオートメーションの導入でよくある失敗が、導入そのものが目的になってしまい、何を解決するために導入したのかが分からなくなってしまうことです。
課題が明確になれば、そもそもマーケティングオートメーションでなくても別のツールで十分だった、ということも起こり得ます。また場合によってはツールの問題ではなく、社内の体制を変えることで解決できることもあるでしょう。
「自社の抱えている○○という課題を解決するために、マーケティングオートメーションの導入が必要だ」という結論に至って初めて、導入を考えるべきです。
2.導入するツール選び
自社の課題がはっきりし、マーケティングオートメーションの導入が必要だと判断したら、どのツールを導入するべきなのかを検討します。
マーケティングオートメーションは国産のものだけでも数多くあり、それぞれに特徴があります。ツールを選ぶときの基準は、どのツールが自社の課題解決に向いているのかという点で考えるべきです。
また、会社によって予算はバラバラなので、予算内で収まるかどうかも重要な検討ポイントです。その際、「◯円までしか出せないからこのツールにしよう」という考え方をすると、失敗のもととなります。
マーケティングオートメーションには高価なものから安価なものまで幅広くありますが、「安いから品質が悪い」「高いから高性能だ」とは限りません。「自社の課題解決ができるか」「搭載された機能に過不足はないか」という視点が大切です。
3.カスタマージャーニーの構築
カスタマージャーニーとは、顧客がどのような行動・感情の流れで成約まで至るのかを表したものです。
カスタマージャーニーの構築をすることで、顧客の行動や感情の変化を想定でき、どのタイミングでどんな施策を打てばよいのかが分かりやすくなるのです。
カスタマージャーニーを構築することは、同時にペルソナを定めることにもなります。そしてそのペルソナを導くために、マーケティングオートメーションのどんな機能を使うのかをここで考えます。
カスタマージャーニーの構築については、こちらの記事で詳しく解説していますので併せてご覧ください。
4.社内の役割分担の検討
カスタマージャーニーが構築できたら、どんな機能を使うのかが見えてきます。そしてそのタイミングでマーケティングオートメーションを運用するための役割分担をします。
上述の通り、マーケティングオートメーションは多機能です。そのため、一人が運用を担当するのではなく、複数人で運用をするケースもあるでしょう。
マーケティングオートメーションの運用で考えられる役割だけでも次のものがあります。
- ・運用責任者
- ・顧客管理担当者
- ・リードナーチャリング担当者
- ・Web制作担当者
- ・効果測定担当者
日本の多くの企業ではマーケティング担当が一人しかいないという現状からすると、運用にこれだけの人数を割くのが難しい場合もあるでしょう。その場合は、まず使う機能を絞るか、外部から担当者を募るという選択肢があります。
5.他部署との連携
マーケティングオートメーションの運用担当が決まったら、最後に他部署との連携が必要です。
多くの場合、マーケティング部門と営業部門は別になっていることでしょう。マーケティングは顧客の見込み度を上げ、営業は見込み度が高い顧客のクロージングをするという役割があります。
そのため、特に営業部門との連携ができていないと、せっかくマーケティングオートメーションで効率良く見込み顧客を創出できても、肝心の成約に繋げられないのです。
具体的には、ホットリードが検出できたあと、そのリードをスムーズに営業へ引き継げるような体制作りが必要です。
また、マーケティング担当が見込み度が高いと判断しても、実際はまだ購買意欲が高まっていなかったというケースも考えられます。マーケティング担当と営業とでの見込み度のズレを少なくするため、見込み度の基準(スコアリング)について随時見直しができるようにもする必要があります。
マーケティングオートメーション導入時の注意点
最後に、マーケティングオートメーションを導入するときの注意点についてまとめました。
- 1.設計をおろそかにしない
- 2.人的リソースを確保する
- 3.スコアリングは随時見直す
- 4.コンテンツが十分準備できているか
1.設計をおろそかにしない
マーケティングオートメーションの導入で最も重要なのが、目的や目標、ペルソナ、カスタマージャーニーなどの設計をしっかりすることです。
前述の通り、目的があやふやだと何のためにマーケティングオートメーションを導入したのか分からなくなります。さらに、目標値がないと進歩しているのかが分からず、モチベーションの低下につながります。
またペルソナやカスタマージャーニーが明確でないと、具体的な施策が定まらないため、思うような効果が得られないでしょう。
このように、マーケティングオートメーションを導入する際には、さまざまな設計をしっかり行う必要があるのです。
2.人的リソースを確保する
またマーケティングオートメーションの運用には、前述の通り人的リソースが必要です。
ここで言う人的リソースとは、単に人数のことだけでなく、マーケティングに対する知識を持っている人材のことでもあります。
マーケティングは奥深いものであり、別の業務の片手間で行えるものではありません。熱意や知識を持ってPDCAを回す必要があるため、意欲的な人材が必要です。
もし現段階でマーケティングの知識がない場合でも、運用しながらでも知識を付けられます。そのため、ここでは知識よりも意欲のほうが重要です。
3.スコアリングは随時見直しが必要
マーケティングオートメーションの運用において、特に難しいのは顧客の見込み度を測る「スコアリング」です。
スコアリングは、「こういう動きをしたら○点」という形で行動や属性に応じて点を付けて、その合計点が基準を超えたリードを見込み度が高いホットリードとして扱います。
しかし、本当に見込み度が高いかどうかは実際に営業をかけてみないと分からないものです。そのため、ホットリードとして検出されたが、実際にはそこまで購買意欲が高くなかったということもあり得ます。
スコアリングは最初からうまくいくことはほぼなく、営業とのすり合わせを繰り返して精度を上げていきます。そのため、スコアリングは一度設定して終わりではなく、常にアップデートし続ける必要があるのです。
4.コンテンツが十分準備できているか
マーケティングにおいて、WebサイトやLP、メールやホワイトペーパーなどといったコンテンツは必要不可欠です。
仮にマーケティングオートメーションの設定をしっかりしても、コンテンツが不十分だと思うような結果は出ないでしょう。マーケティングオートメーションでは顧客の管理や分析はできますが、実際に見込み度を上げるのはこれらのコンテンツだからです。
そのため、マーケティング活動をするためにはコンテンツを生産するための体制作りも重要であると言えます。
マーケティングオートメーションを導入しよう
この記事では、マーケティングオートメーションの導入の流れと注意点についてお伝えしました。
マーケティングオートメーションの導入で最も重要なのは、目的やペルソナ、カスタマージャーニーなどの設計です。これらを整理することで、課題ややるべきことが明確になり、導入後の運用までスムーズに進めることができるでしょう。






