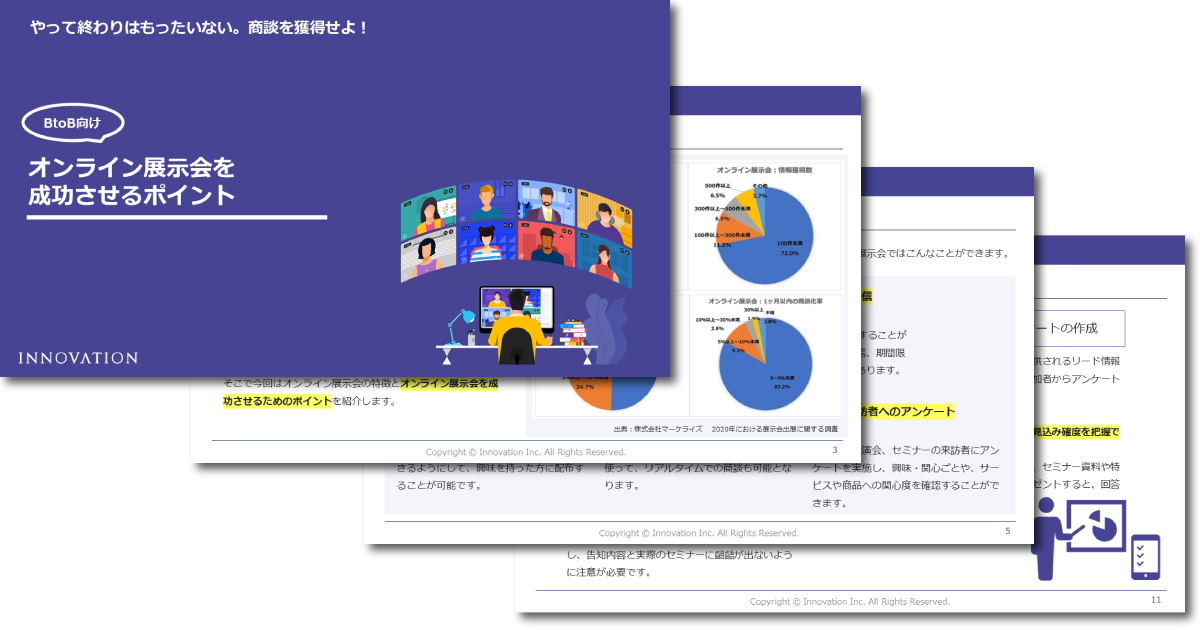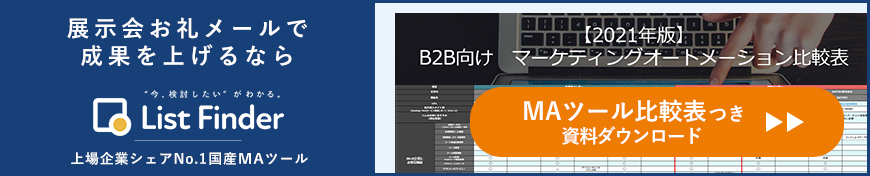展示会後は「お礼メール」で競合に差をつける!

展示会の出展は、直接顧客と会うことができ、一度にたくさんの名刺を獲得できることから有効なマーケティング手段のひとつといえるでしょう。しかし展示会来場者は、情報収集目的の人が大多数で、すぐには購買に至らないことも多くあります。
そこで重要となるのが、展示会後のお礼メール送付や、その後の継続的なフォローアップです。そうすることで、徐々に関心度合いを引き上げ、見込み顧客へと変化させていくことが成果へとつながっていきます。
この記事では、展示会後にお礼メールを送付するメリットから送付のポイント、アフターフォローに至るまで詳しくご紹介します。
展示会は終了後からが本番!
展示会では当日までに出展の準備や名刺獲得目標の設定などたくさんの作業が必要になり、開催当日には来場者の呼び込みやデモ説明など非常に忙しく、最終日の終了後には達成感を感じることができます。
しかし!展示会の本番は当然ながら"展示会後"に始まるわけです。
BtoBの場合、多くの企業が展示会に出展する最終目的は「受注」であり、「売上」につなげることです。BtoBでは商談単価が高額ですから、展示会のその場で「売上」を上げることは難しく、やはり展示会の成果は「名刺の数」であり、「商談になりそうな見込み客の数」あるいは「商談数」となります。これは、展示会は単に受注・売上に至るプロセスの発端でしかないということを示しています。
そのため展示会で獲得した名刺から、受注・売上を創出するまで続く、"プロジェクト"として捉えるべきです。つまり、展示会が終わった時点ではまだプロジェクトの第一段階が終わったに過ぎず、その後に待ち受ける第二、第三段階を見据えて活動していかなければなりません。
来場者にとっての展示会とは?
では、出展社ではなく、来場者は展示会終了後にどのような動きをするのでしょうか。
多くの来場者は展示会で多くの出展社の人に声をかけられるわけです。1,000社単位での出展がある展示会もありますから、来場者にとって展示会場はそれはもう情報の洪水です。日頃からテレビや新聞、スマホ等で情報に対して感度が高い来場者が多いでしょうから、そこに輪をかけて情報が来場者の頭のなかにあふれるのです。
このような来場者にとって、展示会場であなたと話した3分程度の説明はどれほど印象に残っているでしょうか。よほど、具体的に製品検討しているか、御社のことをすでに知っている来場者でない限り、残念ながら展示会終了後1週間も経てば印象からは消え去ってしまうでしょう。具体的に検討している顧客は御社のブースにもやってきますし、競合のブースにも立ち寄ります。このようなお客様との商談は、競合と差をつけるポイントにはなりません。
競合と差をつけるポイントになるのは「1週間後に御社のことを忘れそうな」来場者を長期的に受注・売上に結びつけていくことです。
展示会終了後にお礼メールを送付する目的とメリット
展示会終了後、来場者は情報の洪水の中にいて、次の日からは通常の業務に戻るわけですから、展示会場で見た「今は、たいして興味のない製品説明」は捨て去られそうになります。当然、御社だけでなく競合も忘れ去られそうになっています。
ここで御社の記憶を呼び起こし、自社の商品やサービスへの関心を高めることが「お礼メール」の目的です。
次に、お礼メールのメリットについて見ていきましょう。
メリット①自社や自社サービスを印象付けることができる
展示会で、自社ブースを訪れてくれたとしても、その後、自社や自社サービスについて覚えている可能性は低いでしょう。お礼メールの送付は、忘れかけていた自社のことを思い出してもらうリマインド効果が期待できます。
当日のヒアリング内容や、さらに詳細な資料を添付し送信することで自社のことを思い出し、より印象付けることができます。
メリット②顧客側からのアクションにつなげることができる
お礼メールを送付したことで、自社を思い出してもらったことをきっかけに、自社や自社サービスに興味をもってもらえることもあります。
その結果、問い合わせや、自社サイトへの訪問など顧客側からのアクションにつながることが期待できます。具体的なアクションにより、顧客の興味関心に合わせたアプローチをスムーズに行うことができることもメリットといえるでしょう。
お礼メール送付の前に
展示会後にお礼のメールを送付する際にはまず、獲得した名刺をもとにしたリードのセグメントから行いましょう。
展示会には多くの方が来場し、その目的も様々です。商品やサービスの購入を検討している人もいれば、単に情報収集が目的の人もおり、全ての来場者が自社の見込み顧客になり得る層とは限りません。
そこで、お礼メール送付の際には、顧客のセグメントを行い、自社のターゲットとなり得る顧客を抽出しておく必要があるのです。
お礼メール送付時のポイント
リードのセグメントができたら、メールの作成、送付に移ります。
お礼メールでは、送付のタイミングとコンテンツを押さえることで、より効果的なメールにすることができます。ここでは、それぞれの内容について弊社で実践する上で気をつけていることをお伝えします。
1:お礼メールを送るタイミング
展示会で獲得した名刺の方々の中で具体的に商談が始まるイメージのないお客様にお礼メールを送るタイミングは、ズバリ!お会いした「翌営業日」か「翌々営業日」です。
これは展示会で知った内容を忘れない状態で、早すぎないというのが最適なタイミングです。早ければ早いほうがいいよね?という声が聞こえてきそうですが、当日中に送付すると展示会場で開封されてしまう可能性が高く、展示会場で得た情報と同一視されてしまいます。
ポイントは展示会で得た情報の中から、「頭ひとつ抜き出ること」で、展示会が終わった後に業務中に見ていただけるタイミングが最適と考えています。
ただ、この時に展示会でも紹介した製品情報だけを送っても効果薄です。なぜなら、メールを受信する人はまだ具体的に製品検討する人ではないからです。そのような人でも興味を持ってメールを開封、閲覧してもらう仕掛けが必要です。
2:開封率を高めるタイトルと配信元の設定
開封率はタイトルと配信元でほぼ決まります。できる工夫としては配信元を○○事務局というような個人ではない配信元にするのではなく、「株式会社○○ 田中太郎」というような個人とすると、開封していただける確率が上がります。
また、タイトルも「展示会場での御礼」という、単調なものではなく、セミナー招待やWebの読み物への誘導等、ターゲットにする人が興味をそそりそうなタイトルにすべきです。
3:見込み確度に合わせたコンテンツ
セグメントした顧客の確度に合わせてメールを作り分けることも大切です。見込み確度が高い顧客には、展示会での会話をもとに商品やサービスの詳細情報や、問い合わせ先などを盛り込んだ個別メールを送付しましょう。
対して、まだ製品にさほど興味が無い人でも「お、面白そうだな」と思ってもらえる切り口を考える必要があります。弊社では、メールマーケティングセミナーや、営業の効率化の考え方等、製品には直接結びつかないが、ターゲットの方には興味を持って貰えそうなネタを用意しています。
4:自社を思い出してもらうコンテンツ
多くのブースを回った来場者に自社を思い出してもらうためにも、展示会で掲げたキャッチコピーやブースの写真などを盛り込むことが効果的です。思い出すきっかけとなり、さらに自社を印象付けることにもつながります。
5:メリットを提供する
お礼メールの中で、相手のメリットとなる情報を提供することも効果的です。例えば、来場者特典や、役立つ資料の無料配布など、顧客の関心を惹きつけることのできる内容にすることも重要となります。
見込み顧客に変化させる!お礼メール後のフォローアップ
お礼メールは、展示会の後すぐに送るものです。ここでうまく競合から頭ひとつ抜け出ることができても、その後コミュニケーションがご無沙汰してしまっては全く意味がありません。重要となるのは、お礼メール後も継続的にフォローアップを続けることです。
我々は展示会でお会いした方には月に2回はメールにてお役立ちできる情報をお届けしています。当然読まない方もいらっしゃると思いますが、このようなコミュニケーションを継続していくことにより、展示会の「1週間後に御社のことを忘れそう」だった来場者の方は、検討するタイミングで御社のことを想起し、お問い合せしてくるのです。
この活動は最初は成果が見えにくい割には根気の必要な仕事です。だからこそ、競合に差をつけるポイントになるのです。皆様も競合に先んじてこのような活動にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
これを読んでもっとUrumo!
この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。