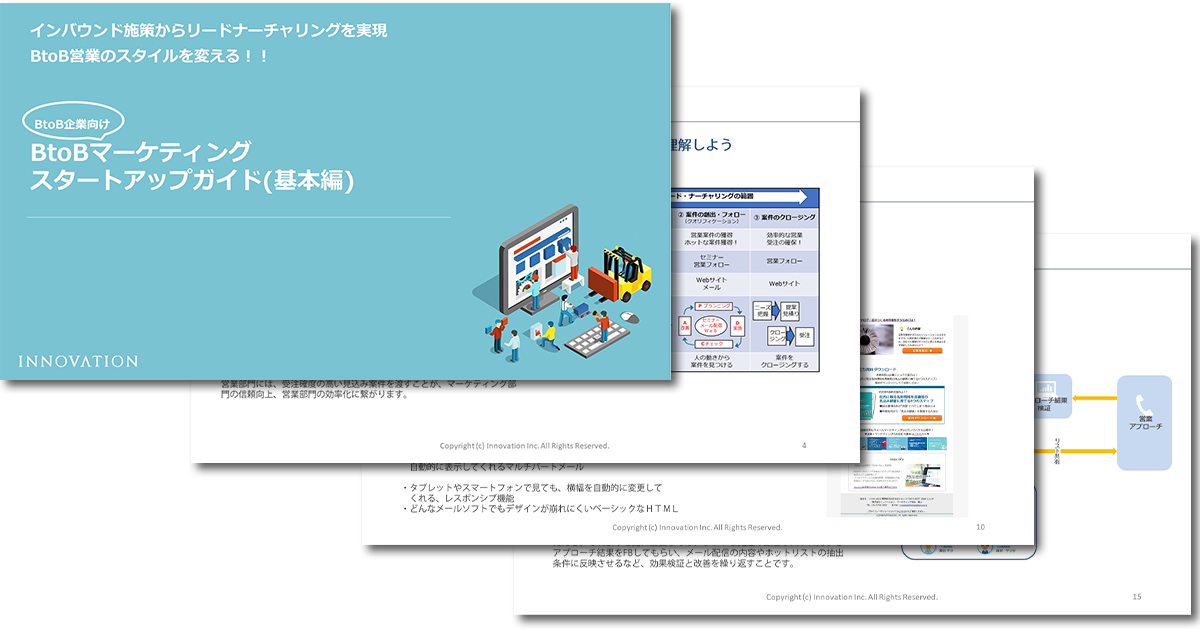Withコロナ時代、BtoBでリードを集めるためにできること(2)

新型コロナウィルスが猛威を振るう中、「ニューノーマル」という言葉が生まれたように、"以前の日常に戻る"のではなく、感染防止を意識しながら新しい生活様式やビジネスの環境を作っていかなければならないという情勢になっています。
そんな中、展示会やセミナーなど、リアルイベントでのリード獲得が重要な施策とされていたBtoB市場も、大きな岐路に立たされています。
ここでは、Withコロナ時代に商談を生み出し続けるために取り組むべきことについて、3回に分けて解説していきます。
第2回めの今回は、前回の記事「Withコロナ時代、BtoBでリードを集めるためにできること(1)」で整理した3つの課題に対して、解決のための打ち手を詳しく解説していきます。
【集客】の課題を解決するための打ち手
◆ウェビナー(オープン型)
今回、コロナによる3密防止から一気に認知が高まったシステムですよね。利用用途も幅広く社員総会、新卒説明会、決算発表といった採用・広報に関するものから、カンファレンスや異業種交流会、ミートアップ(フランクな交流会)といった営業関係でも幅広く利用されることが多いです。
元々の語源はお察しの通り「WEB+セミナー」の造語。リアルでセミナーを実施していた会社も今ではウェビナー開催が一般的になりつつありますね。有名なZoomやCocripoといったシステムなど多数出てきており、これまで準備に関する手間や場所をおさえるコストを気にすることなく、手軽に実施できるところもお勧めです。
テレワーク環境が整い始めた昨今では気軽に参加者も手元のPC・スマホから入室できるため、集客の入口としても集まりやすい対策です。入口が広いため"オープン型"になります。1つ注意点は、セミナー用のコンテンツが当たり前のように必要になります。リアルと違いウェブでは飽きられやすいので、30分以内のショートVer.でスリムにまとめた方が良いでしょう。スマホで閲覧する参加者のことを考え、文字を大きく、図を豊富に使うこともポイントです。また、最近では"ラジオ感覚"でPCからバックグラウンドで作業しながら参加される方も増えているため、抑揚のない雰囲気で開催するのは微妙です。
カジュアルな内容かつ問いかけによる双方向性を意識しましょう。また、配信するコンテンツの内容にこだわることも大切です。
- ・滅多にお目にかかれない業界の専門家やエキスパートを呼ぶ
- ・専門的かつすぐに使える知見/ノウハウを共有する
- ・書籍やWebにあまり書かれていない情報をフックに取り上げる
- ・斬新なテーマを用意する
これらも心がけてみていただくことをお勧めします。
ウェビナーに使えるツール例
- Cocripo(コクリポ)
- 通信環境の安定性やセキュリティに拘ったツール。トライアル環境から始めることもできるので、まず手始めに感触を掴んでみたい方にもお勧め。
◆リード獲得媒体
専門性が高いBtoBにおいては、リード獲得を目的とした媒体などに自社製品/サービスを掲載してみるのもお勧めです。媒体によって広告枠やオプションによるPR内容が変わるので事前に調べて不明点は営業担当者に聞けば良いでしょう。最近は成果報酬型の外部媒体も多いため、最初はリスクなく小さくスタートすることも可能です。
自社の製品の利用ユーザーが多い場合はレビューを中心に製品/サービスを紹介できる媒体もあるので、この機会にお客様からの評価をまとめて新しい集客のきっかけを見直してみるのも良いですね。
リード獲得媒体の例
- ・ITトレンド
- ・IT Review
- ・ボクシル
◆SNS
最近はスマホから情報収集をする企業担当者も増えてきており、SNSをビジネス活用する企業も増えてきています。特にビジネス界隈ではFacebookやTwitterがお勧めです。
採用も広義の意味での集客と考えた場合、最近「Twitter採用」という言葉も出てきており、中途募集・新卒・インターン募集にも向いています。利用者が比較的若年層で情報感度が高かったり、働き盛りの20-30代がメインの利用者層といった点も相性が良い点として考えられます。
Facebook広告は綿密なターゲティング設定ができるため、深く利用希望者へ届けたい時に効果的です。特に前段のウェビナー参加をコンヴァージョンに置いた際のCPAは数千円で取れることもあります。
Twitterは即時性が高いため、ウェビナーを始めとしたイベントの案内や導入事例(プレスリリース)の紹介など、スピード感を持って取り組めることから早期拡散効果にも期待できます。
運営はマーケティングの部署が担当するケースが多いですが、スタッフを巻き込んで皆で投稿内容を考えたり発信することもできるため、組織内の製品/サービスの見直しや関係者のエンゲージメント効果を高める作用もあります。
◆Webカンファレンス
最近、「テレカン」と言われることもありますが、Withコロナ時代はオンラインでのイベントが日夜業界ごとで開催されています。
テーマや業界と様々な切り口がありますので、広く集客の間口を取り認知を取りたいのか、ある程度絞り込んだ層を狙っていきたいのか、自社の戦略に沿って参加してみることで新しい販路につながる機会もあるでしょう。
◆ポスト系メール
テレワーク推進による在宅率が高まるコロナ時代の社会では、これまで当たり前だった営業パーソンの電話や対面訪問が難しくなってきました。
そんな時はメールを営業マンの代わりに活用して集客機会を作りましょう。例えば各企業のフォームへ投げ込む(ポスト型)のアプローチ手法でイベントの各種案内、お客様の声、導入事例やプレスリリースの案内など、気になる企業へアプローチしてみるのも一つの手です。
最近ではアポイント取得までつなげられるサービスも多く、成果報酬でリスクなく小スタートを切れるサービスもリリースされています。
ただし、「営業お断り」と注意書きがされているフォームに投げ込んだり、同じ会社に何度も投げ込んだり、全く自社サービスと関係性がなさそうな企業に投げ込むのはやめましょう。場合によってはトラブルにもつながりますので、慎重な準備が必要です。
例えば、自社のWebサイトに何度も来訪しているなど、興味がありそうな企業にアプローチしてみるのは良いかもしれません。IP解析ができるツールや、弊社のList FinderのようなMAツールを使いながら、アクセス分析し自社製品へ関心が高そうな企業へコンタクトを取りにいくことも可能です。
ポスト系メールサービスの例
SHINOBI mail
◆アポイント獲得代行(紹介系)
最近はフリーランスや副業ブームのため、会社の一スタッフとしての肩書以外に様々な業界や企業担当者と接点を持つビジネスパーソンの方が増えていますよね。
そんな現代の特徴をうまく捉えたサービスとして、自社のターゲットとなる担当者(人事・営業・マーケ・情シス部など)とのアポイントを代行で設定してくれる"つながり系紹介"サービスも出てきました。
自社の製品/サービスを理解してくれている方からのアポイントにより、より集客後の提案機会の質も上がることから注目されています。
もし、従来の集客方法にマンネリ感、効果に限界を感じられた場合には視点を変えて利用してみることをお勧めします。
紹介系アポイント獲得代行サービスの例
Saleshub
【育成】の課題を解決するための打ち手
◆ウェビナー
前段でご紹介したウェビナーですが、集客だけではなく見込み顧客の育成でも使えます。
「ウェビナー=セミナー」には主に2種類あり、①オープン型②クローズ型があります。
①は【集客】の項目で紹介したものですが、【育成】で活躍するのは②のクローズ型です。
例えば見込み顧客のリードに対して①で"ツカミを取った後"により具体的な運用事例の紹介や活用提案のコンサルティング事例など一段深い情報を提供することで参加者の興味度合いを高めることが可能です。
最近では既存顧客向けのワークショップや説明会として活用し、顧客満足度を上げるために開催されるケースもあります。こちらも広い意味では「育成」にあたりますよね。
ウェビナー後はさらに興味がある(詳しい話を希望する)方に個別相談や商談に持ち込むことも可能です。大切な機会となるため、ここでのウェビナーはリハーサルや配信コンテンツの構成を磨くなど、社内の関係者と協力して準備を進めていきましょう。
補足/運営する際の工夫点
限定〇名などある程度、参加人数を絞り込み、小規模で対話できる人数を前提で開催すること。また、定期的に案内するため週に一回など「開催頻度を帯にする」ことも有効です。
◆メールマーケティング
コロナ時代において非接触の営業/マーケティング活動において、メールでの育成が上手くできるかどうかで今後その企業の生産性に大きく左右するといっても過言ではありません。
ポイントになるのは、「内容」と「効率性」です。内容はお察しの通り、営業パーソンの代わりに啓蒙・興味喚起をする訳ですから今一度自社のUSP(サービス優位性)を分析し、ターゲットにあわせた訴求の型を数パターン設けておくと良いです。
加えて大事なことが「効率性」です。どれだけ良い内容でもメールマーケティングの開封率やコンバージョンを考慮すると定期的に配信することが前提となりますので、作業に毎回多くの労力が負担としてかかるとなかなか現実的ではありませんよね。
世の中には様々なメール配信システムがリリースされているので、自社の役割分担や担当者の業務レベルやキャパシティを考慮することを選定の基準に置くことをお勧めします。
最近ではさらに一歩進んでMAツールで配信内容をステップ形式=シナリオ(受信側の行動履歴から次回配信するメール内容の仕組み化)として稼働させることも可能です。
弊社でも以前メールマーケティングのポイントについてまとめておりますので、お時間があるときにご覧ください。
◆SNS活用
一般的にBtoBではSNSがあまり合わないと言われています。代表的な例として、世界的に普及しているといわれるLinkedInもここ日本ではそこまで浸透していない印象です。
では、なぜ【育成】であえてSNSを取り上げているかと言うと、なぜなら、キーパーソンとのコミュニケーションを取る手段として、有効な場合が存在するためです。
一つのサービスを導入するにも、例えば決裁者・推進者・情報収集者・ゴールキーパー(リスクヘッジ担当)・アナリスト(分析担当)と、成約に至るまでに複数の関係者の合意を取る協議を重ねながら進めていくのがBtoBの一般的な特徴ですよね。
そこで思うように案件が進捗しない時に、もし先方の決済者とSNSでつながっていれば、気軽にDMを送ることができるTwitterやFacebookメッセンジャーでダイレクトに相談することもできます。
実際に水面下で仕事の相談や依頼など商談につながる機会がメッセージでやり取りされていることがビジネスの世界では多くあります。
最近では影響力のある社員が発信するだけで、瞬時にイベントが満員になることもあります。1人1人が発信力を持つことで、そこでつながった情報のやり取りはオープンでもクローズでも活用できる時代になっています。
Twitterを始め、SNSが普及し誰もが発信者になれる時代です。"評価経済"といった言葉もあるように、個人ベースでどれだけインフルエンサーとしてのポテンシャルがあるかは、新しい施策として今後益々注目を浴びるはずです。
この機会に社員の方々が自発的に発信できるような文化の醸成に目を向けることで、 コロナ時代における絶好の育成施策へのヒントをつかむのはいかがでしょうか。
これを読んでもっとUrumo!
この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。