話題の「リードナーチャリング」が注目されている背景
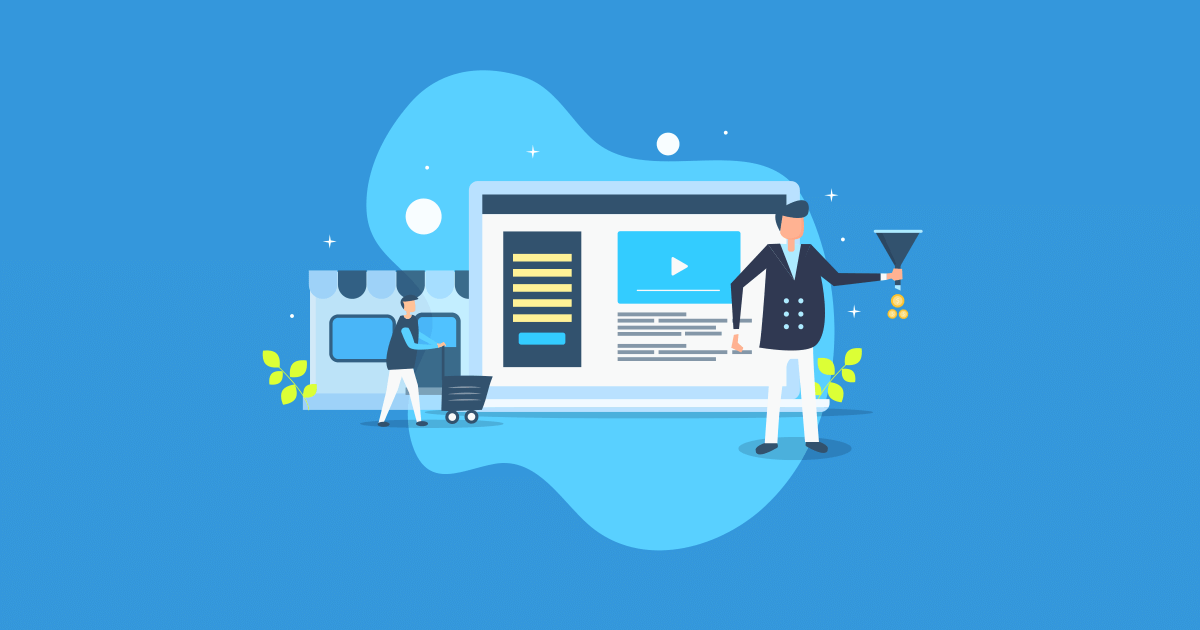
最近、BtoBマーケティング・営業の手法で「リードナーチャリング」や「見込み顧客育成」というキーワードが多く聞かれるようになりました。今まではよく「リードジェネレーション」や「見込み顧客獲得」など、新規の獲得に関わるキーワードや施策がよく話題にあがっていましたが、なぜ近年になって「リードナーチャリング」が注目されてきているのでしょうか。
そこで今回は、リードナーチャリングが注目されている背景についてご紹介します。
リードナーチャリングとは?
リードナーチャリングは日本語に訳すと「見込み顧客育成」となり、自社の見込み顧客と継続してコミュニケーションをとり、有益な情報提供を続けることで、ニーズを顕在化させていく取り組みのことを指します。
これまでは、テレアポやWeb広告などを利用して、直近の営業案件につながりそうな見込み顧客情報を獲得し、営業がアプローチする」という活動が一般的でした。リードナーチャリングは、そのようにすぐに営業的な成果を見込む考え方ではなく「獲得した見込み顧客情報から案件を中長期で創出する」という考え方です。
なぜリードナーチャリングが注目されているのか
では、なぜリードナーチャリングが注目されているのでしょうか。その背景についてご紹介します。
1:インターネットの普及によって、情報量が飛躍的に増加した
インターネットが普及する前は、世の中の商品やサービス、新しい情報を取得する方法が限られていました。多くの企業は、常にオフィスに出入りする他社の営業担当者に相談し、自社に合う商品、サービスを紹介してもらっていました。
しかし、インターネットの普及や通信環境の改善、デバイスの多様化、SNSの普及やキュレーションサ―ビスの登場などにより、欲しい情報を取得したり共有したりする環境が整ってきました。 Web上の情報量が飛躍的に増え、それと同時に「営業担当から情報もらって商品を検討する」という検討方法から、「Webで情報を収集し、比較する」という検討方法に変わってきたのです。
2:Web上でのユーザーの興味や行動の可視化が進んだ
「アクセス解析ツール」もリアルタイムでたくさんの情報が可視化できるようになりましたし、ユーザーの行動や興味、いわゆるデモグラ情報を取得することも可能になりました。
リードナーチャリングを行ううえで重要なポイントとして、「One to Oneマーケティング」があります。これまでの接触履歴やWeb上での行動を可視化し、一元管理しておくことで、見込み顧客それぞれの検討状況にあわせて、適切な情報提供をおこなうことができるようになったのです。
3:さまざまなツールの登場で、継続的なコミュニケーションが簡単に
ひとりひとりの興味がわかったとしても、その興味に合わせてそれぞれ個別対応するには、膨大な工数がかかります。しかし最近ではWeb上の行動に合わせて、その行動にあった広告やメールを自動的に配信できるツールが増えてきています。
それにより、それぞれの興味に合わせた継続的なコミュニケーションが比較的簡単に行えるようになってきたのです。
4:リード獲得方法の多様化により、直近で案件化しにくいリードが増えた
インターネットの普及により、製品比較サイトやホワイトペーパーのダウンロード等、リード獲得をする手段も圧倒的に増加しました。それと同時に、直近では案件にならないような、確度の高くないリードの数も増えてきています。そのようなリードは、少し長い目でフォローや興味喚起をする必要があるので、そのこともリードナーチャリングが注目されている要因のひとつです。
リードナーチャリングの取り組みが進まない背景
これらの背景がありながら、日本のBtoB企業ではリードナーチャリングを実践できている企業はまだまだ多くありません。なぜリードナーチャリングの取り組みが進まないのでしょうか。その理由を解説していきます。
1:目先の受注ばかりに目が行ってしまう
BtoBに関わらず、販売や営業の現場で求められるのは「売上」や「受注数」です。この目標を達成するための近道は「目先のニーズのあるお客様を受注に導くこと」です。そうすると、営業担当はどうしても直近のニーズを受注につなげることに注力しがちですし、マーケティング(営業推進や企画)の立場としても、受注に直結する見込み顧客の獲得以外は優先度を下げてしまう傾向にあります。
2:訪問営業が一般的
リードナーチャリングが先に普及したしたアメリカは国土が広く、全ての見込み顧客と対面で商談を行うことは非常に困難だったため、直接商談を行う見込み顧客は厳選する必要がありました。一方日本では、国土が狭く、地理的に「会って商談することが難しい」と感じることは他国に比べて少ないため、「会って関係性を築く」ことが一般的でした。
「まずは人間関係を構築し、情報交換ができるようになって、1年後に商談の機会が訪れる」という、営業担当自身が工数をかけてナーチャリングのような役割を担ってきたわけです。
3:高度な知識や多くのリソースが必要
リードナーチャリングの重要性を理解し、いざ取り組んでみようと思っても、途中で頓挫してしまうケースもあります。一般的には、見込み顧客を「育成」していくためには、自社のターゲットを定める「ペルソナ設計」や、潜在ニーズから購買までの心理、行動を表す「カスタマージャーニーマップ」を作成することが必要とされる場合が多くあります。
そのような業務に取り組んだことがない企業では、社内に知見がないことも多く、また、リソースを割く余裕がない場合も多いでしょう。
見込み顧客とコンタクトを取り続ける重要性
しかし、インターネットが普及して見込み顧客の購買検討プロセスも変化している今、顧客との定期的なコミュニケーションは重要性を増しています。
欧米のコンサルティングファームの調査によると、直近で受注せず、フォローをやめてしまった顧客のうち、80%は競合他社から製品を導入しているといわれています。機会損失を防ぐ意味でも、リードナーチャリングの実施は、非常に重要度が高いマーケティング施策だと言えるでしょう。
まずはできるところから始める
いきなり高度なツールを導入してリードナーチャリングを実践しようと思っても、それを使いこなせるリソースが社内になければ意味がありません。また、BtoB、とくに中小企業においては、ナーチャリングをするための十分な見込み顧客数がない場合も多くあります。
そのような場合は、まずは「自社の見込み顧客と定期的にコミュニケーションを取る」ということから始めてみてはいかがでしょうか。展示会や広告施策で集めた見込み顧客リストや、過去失注となった案件、過去に自社サービスを解約した企業などのリストを一元管理して、定期的にメールを送るのも良いでしょう。
見込み顧客が再度商材の検討を開始した際、送られたメールをきっかけにあなたのサービスを思い出すかもしれません。それによって再度提案の機会を得られれば、機会損失を防ぐことに繋がります。
さいごに
リードナーチャリングの重要性は高まっていますが、いきなり高度な取り組みを始めようと思ってもうまくいかないことが多いでしょう。まずはスモールスタートをして、PDCAサイクルを回しながら自社の中で成功パターンをつくることから始めることが重要です。
市場には、安価に始められるツールも多く出回っています。これからリードナーチャリングを始めようと思っている方は、ぜひそれらのツールを検討してみてください。
これを読んでもっとUrumo!
この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。





