リードナーチャリングにおけるKPI設計方法は?BtoBでの具体例も紹介

リードナーチャリングを行ううえで重要なのは、成果を確かめるための指標設定です。適切にKPIを管理することができれば、評価がしやすくなるのです。そこで、この記事では、今一度リードナーチャリングについて理解を深め、適切なKPI設計のポイントについて解説します。
- ▼この記事でわかること
- ・リードナーチャリングの概要と注目されている背景
- ・リードナーチャリング施策ごとのKPI設計例
- ・KPIを正しく設計する方法
- ・MA(マーケティングオートメーション)を活用したKPI管理の効率化
リードナーチャリングとは
まずは、リードナーチャリングについておさらいしておきましょう。リードナーチャリングとは、見込み顧客を育成することです。
展示会やイベント、コンテンツマーケティング、Web広告などで集めたリードに対し、メールやセミナーなどの施策を通じて、有益なコンテンツを継続的に提供し続けてコミュニケーションを取ることで、検討度が上がったタイミングを判別し、商談につなげる活動のことを指します。
リードナーチャリングが注目されている背景
これまでは、製品の導入検討をする際にはまず営業担当に問い合わせをするのが主流でした。しかし、インターネットの普及により、顧客が自分で能動的に情報収集するようになったため、実際に企業に問い合わせが入る頃には、顧客は粗方の導入検討を終了していることも多くなりました。
こうした市場の環境下でも顧客との信頼関係を築き、自社を選んでもらうために、早い段階で顧客に接触し、顧客の見込み度合いを高めていくリードナーチャリングの手法が求められているのです。
リードナーチャリングにおけるKPIの重要性
リードナーチャリングを効果的に進めるためには、「何をもって成功とするのか」を明確にすることが欠かせません。ナーチャリングの目的は、単なる情報提供ではなく、見込み顧客の購買意欲を育て、最終的に商談や受注へとつなげることにあります。そのプロセスは複数の施策と接点を経て進行するため、成果を定量的に把握できなければ、適切な判断や改善が困難になります。
そこで必要になるのがKPI(重要業績評価指標)です。KPIを設定することで、リードナーチャリングの各施策がどの程度機能しているかを定量的に把握でき、ボトルネックの特定や施策の見直しが可能になります。
また、KPIはチーム内での共通認識を築くうえでも有効です。営業・マーケティング・インサイドセールスなど複数部署が関与するナーチャリング施策では、KPIを通じて評価基準を統一することで、連携がスムーズになります。KPIの設計と運用は、リードナーチャリングの質を左右する重要なステップなのです。
KPI設計方法
ここでは、KPIを設定する手順について見ていきましょう。
1.KGIの設定
KPIを適切に設計するためには、まずKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)を明確に設定する必要があります。KGIとは、組織やプロジェクト全体の最終的なゴールを数値で表したものです。
リードナーチャリングにおけるKGIは「受注件数」や「商談化率」、「売上金額」などが該当し、ナーチャリング活動の最終成果を測る指標になります。
このKGIが設定されていないと、各施策の指標(KPI)も単発的で散漫なものとなり、施策が全体の目的に貢献しているのかが判断できなくなります。まずは、マーケティング・営業部門で共通のゴールとしてのKGIを明確に設定しましょう。
2.KGIの要素分解で指標を明確にする
設定したKGIを具体的な行動指標に落とし込むためには、「要素分解」が有効です。これはKGIを構成する要因を細分化し、それぞれを定量的に捉えるプロセスです。
たとえば、「月間10件の商談創出」をKGIとした場合、それに至るプロセスは以下のように分解できます。
- 1.月間ウェビナー参加者数
- 2.ウェビナー後のアンケート回収率
- 3.フォローアップメールの開封率
- 4.テレアポによるアポイント獲得率
このように、KGIを分解することで、具体的に追うべきKPIが浮かび上がります。KGIの要素分解は、ナーチャリング施策を数字で管理・改善するための出発点です。
3.KPIの設計方法
KPIとは、KGIを達成するための中間的な評価指標です。ナーチャリングの過程では「見込み顧客との接点の質と量」に関わるあらゆるデータがKPIになり得ます。
KPIを過度に多く設定しすぎると運用負荷が上がり、重要指標が埋もれてしまうリスクがあるため、優先度の高いものから段階的に設計・導入することが重要です。
KPI設計に役立つ「SMART」の法則
KPIを設定する際に活用できるフレームワークが「SMART」です。これは5つの要素を基準にして、達成可能で意味のある目標を定めるための設計指針です。
- S(Specific)具体的であること:曖昧な表現ではなく、誰が見ても明確な内容にする。
- M(Measurable)測定可能であること:数値で追える指標を選ぶ。
- A(Achievable)達成可能であること:現実的で、チームの努力で実現できる範囲にする。
- R(Relevant)関連性があること:KGIやビジネス目標と直結していること。
- T(Time-bound)期限が定められていること:評価のタイミングが明確であること。
たとえば、「3カ月以内にナーチャリングメールの平均開封率を25%に引き上げる」という目標は、SMARTの要件をすべて満たしています。
リードナーチャリングを成功させる、KPI設計例
KPIとは「Key Performance Indicator、重要業績評価指標」です。最終目標であるKGI(Key Goal Indicator、重要目標達成指標)に対し、KPIは目標達成に向けた中間指標となります。
リードナーチャリングの場合、活動のゴールは商談数の増加であり、そのための手法は主にメールやセミナーが挙げられます。そこで、メールやセミナーで設計すべきKPIを具体的に紹介していきます。
メール配信での主なKPI
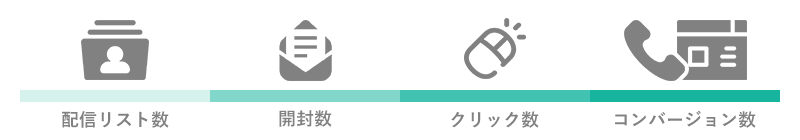
- メール配信リスト数
- メールを配信できるリスト総数です。
そもそも配信リスト数が少なければ、そこから獲得できるCV数は少なくなります。そのため日頃から営業活動などでメールを送れるリードを多く獲得しておくことが重要です。
- メール開封数
- 配信したメールが開封された数を示す数値です。
この数値はHTMLメールのみでしか測定できないものの、メールの内容に関心があるのか、件名は興味喚起ができているのかを把握するうえで有用な指標です。
- クリック数
- 配信したメール本文に含まれるURLがクリックされた回数です。
メール内に自社製品の紹介サイトや、価格や導入事例を記載したWebページへ誘導するリンクを設定し、見込み顧客の興味・関心を図ることが可能です。
- コンバージョン(資料ダウンロード・お問い合わせなど)数
- メール配信の最終的な成果指標となります。
総配信数に対してお問い合わせなどのアクションがあった割合を指し、配信したメールが適切だったかどうかの判断の基準になります。
テレアポでの主なKPI
- リスト数
- リスト数とは、架電の対象となる見込み顧客の数を指します。
どれだけ優れたトークスクリプトや営業力があっても、リストが十分でなければアプローチのチャンスが限られます。また、リストの「量」だけでなく、「質」も成果に大きく影響します。
- 架電数
- テレアポ担当者が実際に行った電話の件数です。活動量そのものを測るKPIであり、日・週・月単位で目標値を設定しやすい指標です。
商談数の最大化には一定の架電量が不可欠であるため、まずは「数を打つ」ことが成果につながる第一歩です。
- 通話時間
- 通話時間は、見込み顧客とどれだけ深いコミュニケーションが取れたかを推し量る定性的なKPIです。
通話が極端に短い場合は、関心を持ってもらえていないか、トーク内容に問題がある可能性があります。一方で、長ければ良いというわけでもなく、「適切な時間で有意義な情報を伝えられているか」がポイントです。
- 商談数
- 架電の結果として商談化した件数をカウントすることで、活動の最終的な目的(KGI)とのつながりを把握できます。
この数値が低い場合は、トークスクリプトや対象リストの見直しが必要です。営業チームとの連携においても、この指標は評価・改善の軸になります。
セミナー開催での主なKPI

- セミナー集客数
- セミナーへの参加申込数です。
集客数の最大化だけを目指して、自社サービスとの関係が薄いテーマを企画してしまうと、その後の商談創出などに悪影響が出てしまいやすくなるため、しっかりと目的を意識してテーマを企画するようにしましょう。
- セミナー参加数
- 集客数に対して出席率が何%なのかが指標となります。
参加しやすい時間帯を選んで開催したり、リマインドメールを送るなどで改善することができます。
- アンケート回答数
- 出席してくれた人数に対して実際にアンケートに回答してくれた人数です。
間接的に、「セミナーテーマが参加者にとって有益なものだったか」を測る指標となります。
- 有望回答数
- セミナー開催での最終的な成果指標となります。
アンケート回答の中から自社製品に興味のあるリードをピックアップし営業にトスアップできる数字となります。
このように段階的にKPIを設定し、適切に管理することで営業へのトスアップができるリードにつながるでしょう。また、リードナーチャリングは「営業部門にリードをトスアップして、商談数を増やす」ことが目的のため、「リードナーチャリング施策によって獲得できた商談数」を検証するようにしましょう。
設定したKPIを達成するために
効果的なリードナーチャリングを行うためにも、数値化できる明確なKPIを設定することが重要です。達成したい目標(商談数の増加)に対して整合性があり、誰が見ても理解できるシンプルで測定可能な目標にすることでゴールに向かいやすくなります。
KPI設定をした後も、PDCAサイクルを回し実際に改善できているのか、そうでないとしたら何が原因なのか、現状を分析してみましょう。では、例として、実際にメール施策でのPDCAを確認してみましょう。
P(plan)計画を立てる
メール配信前に、配信の目的やKPIの設定を行います。
D(do)実行する
メールを配信します。
C(check)検証する
配信後、ユーザーがどう反応したのかを数値化して、効果があったのか、なかったのかを測定します。KPIが達成できていなければ、原因を追及し改善してみましょう。
A(action)改善する
「なぜこのような結果になったのか」という観点から改善点を明確にしましょう。改善の仕方について、開封数とクリック数を例に挙げご紹介します。
- 開封数
-
メールの開封率の場合はメール開封前に目にするタイトルに問題があったと推測できます。いかに本文を見たくなるようにするかが大切です。読むことで得られるメリットをストレートに訴求したり、具体的な数字を使って訴求するなどさまざまな工夫をしてみましょう。
配信の度に開封率の分析を進めて、見込み顧客がどんなことに興味があるのか、どんなタイトルであれば開封しやすいのかを把握し、改善していきましょう。
- クリック数
-
文章が長いメルマガの場合、途中で読むのを止められてしまう場合が多く、せっかく記載しているURLもクリックしてもらえないでしょう。メールの文章は簡潔で読みやすく、続きが気になる内容にまとめ、詳細をリンク先で確認できるようにしましょう。
配信時間の設定も重要です。受信者となる見込み顧客が最もメルマガを見てくれそうな曜日や時間帯を推測し、最初はあえて複数のタイミングのパターンで配信してみましょう。
このように問題点を洗い出し、今後の施策を考え継続的に向上させていくことで着実にKPI達成へと近づくことができます。
KPI管理にはMAの活用が効果的
リードナーチャリングにおいてKPIを効果的に管理・改善していくには、MAツール(マーケティングオートメーション)の活用が有効です。
ナーチャリング施策では、メール配信、Web閲覧、セミナー参加、資料ダウンロードなど、さまざまな顧客接点が存在します。これらを個別にExcelなどで手作業管理していては、データの一元化が難しく、KPIの進捗確認やPDCAの高速化に支障が出てしまいます。
MAツールを導入すれば、以下のような機能によりKPI管理が効率化され、施策の改善スピードが飛躍的に向上します。
MAでできるKPI管理の具体例
- ・メールの開封率・クリック率の自動測定
- ・特定のアクションのトラッキング
- ・リードのスコアリングとステージ判定
- ・レポート機能による可視化と共有
たとえば、「セグメントごとのメール開封率」や「ダウンロード後3日以内に商談化した割合」など、細かなKPIを可視化することで、どの施策が成果に寄与しているかをデータで判断できます。
また、KPIの未達が見込まれる場合には、自動アラートやシナリオ変更機能を活用することで、素早い打ち手を打つことも可能です。
結果として、MAは「KPIのリアルタイムモニタリング」と「施策の改善」を両立させる強力な基盤となり、リードナーチャリング全体の質とスピードを大きく引き上げてくれます。
MAツールについては、以下の記事も参考にしてください。
【初心者向け】マーケティングオートメーション(MA)とは?できることや導入のメリットを紹介!
リードナーチャリングで成果を出すには
ここでは、KPIを管理するだけで終わらせず、ナーチャリング活動を成果に結びつけるために意識すべき考え方について解説します。
KPIの先にある「顧客との関係構築」
リードナーチャリングの本質的な目的は、「今すぐの受注」ではなく、「中長期的な信頼関係を構築すること」にあります。どれだけ多くのメールが開封され、どれだけセミナーに参加者が集まっても、それが顧客にとって価値ある体験でなければ、最終的に商談や受注にはつながりません。
KPIはあくまで行動の量や変化を示す指標にすぎません。一方で、「この企業なら信頼できる」「この担当者と話を続けたい」と思ってもらえるような関係性の構築は、数値には表れにくい価値といえます。
たとえば、メールの開封率がさほど高くなくても、特定のリードが毎回興味を持って反応してくれていたり、セミナーの少人数参加者のうち何人かが深い興味を持ってくれていたりすることがあります。こうしたサインを見逃さず、リード一人ひとりとの接点を大切にする姿勢が、最終的な成果に直結します。
KPIに振り回されないための視点
KPIは非常に便利な管理指標ですが、「KPIを達成すること」自体が目的化してしまうと、本末転倒になりかねません。本来、KPIはビジネスの目的に近づくための手段であり、「顧客の課題を理解し、最適な情報を提供する」ための指針であるべきです。
たとえば、「メール開封率を上げたいから」といって、誇張した件名で無理に開封を促した結果、逆に信頼を損なってしまうような施策は、長期的な関係性に悪影響を与える可能性があります。
KPIは定量的に評価できる一方で、その背景にある顧客心理は定性的な視点で補完する必要があります。数値に一喜一憂するのではなく、「この数字は何を意味しているのか」「顧客との関係にどう影響しているのか」という問いを常に持つことが、KPIに振り回されないための鍵となります。
まとめ
中長期的に行うことが必要なリードナーチャリングにおいて、ゴールである営業へのトスアップまでの道筋を見失わないためにも、中間目標であるKPIの設定をすることが重要となります。適切なKPIの設定をし、成果を実感できるリードナーチャリングにしていきましょう。






