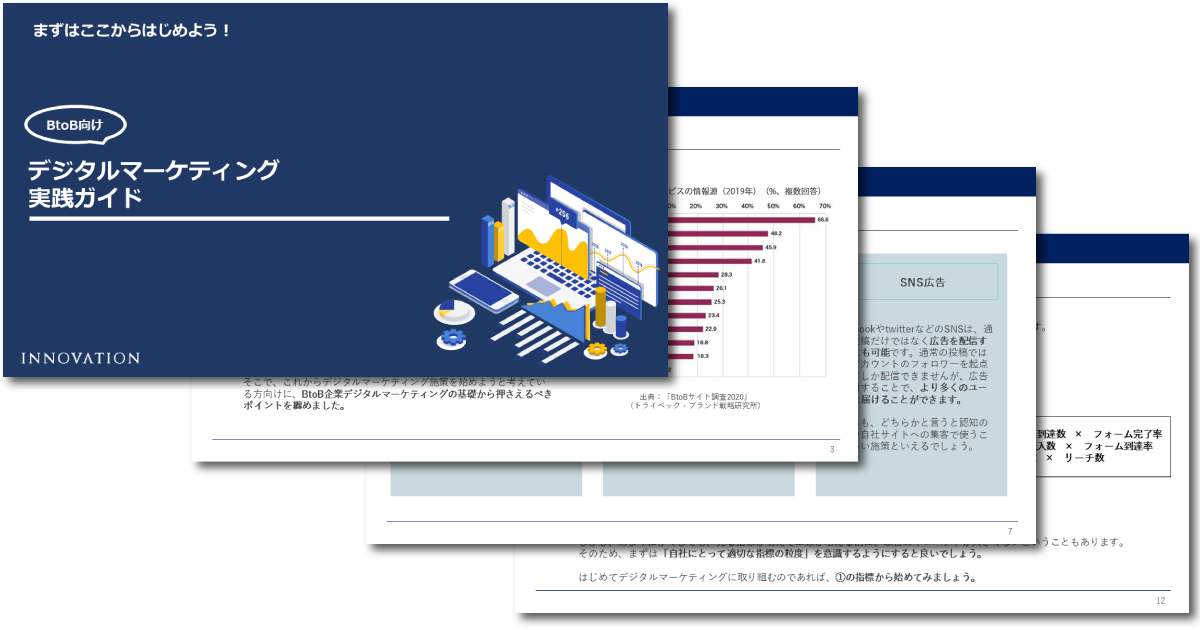いまさら聞けない「DSP」とは?~運用実践編~

DSPという言葉の意味は知ってる、だけどどうすれば成果が出るのかさっぱりわからない・・・。そんな方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、DSP広告を実際に運用していく上で押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
DSPについておさらい
まずはDSPについて、その仕組みやメリットなど基本的な知識をおさらいしておきましょう。
DSPとは、Demand-Side Platformの略称で、広告主(広告配信を希望している側)のプラットフォームです。
インターネット広告の配信技術が進化していくに従って、より適切なユーザに、彼らのニーズに合った広告を配信したいという思いが強くなっていきました。しかし、それを人力でおこなうには非常に工数がかかってしまうため、効率的に配信できるための仕組みとして登場したのが、DSPなのです。
DSPの仕組み
DSPによる広告配信は大まかに以下の仕組みで行われています。
- ユーザが広告枠のあるサイトを閲覧
- ユーザ情報をもとに、SSPに広告をリクエスト
- SSPがDSPに、配信する広告を決めるオークションのリクエスト
- 各DSP内による入札の結果情報をSSPに送信
- 落札したDSPの情報をサイトに送信
- サイトが落札したDSPに対して、広告配信のリクエスト
- DSPからサイトに広告配信
DSPを利用するメリット
DSPによる広告配信には多くのメリットがありますが、代表的なものとして以下の3つがあります。
- ・興味関心の高いユーザにターゲットを絞り、広告配信することができる
- ・類似ユーザをターゲティングして、広告配信することが出来る
- ・広告運用者の工数削減
DSPの仕組みやメリットについては、以下の記事内で詳しく解説しています。気になった方はぜひご覧ください。
運用する前に押さえておきたい、DSPのターゲティング方法
DSPの仕組みがわかったからと言って、すぐに成果を出せるわけではありません。どのようなユーザに対して広告配信するかという「ターゲティング」が非常に重要です。
まずは、DSPで具体的にどのようなターゲティングができるか、見ていきましょう。 その条件は、大きくユーザの「環境」「属性」に分類することができます。
ユーザの環境
広告を閲覧するであろうユーザの環境をターゲティングすることができます。条件として一般的なものを以下に挙げました。
- 配信デバイス
- PC、モバイル、スマートフォンなどの条件でターゲティングできる場合が多いようです。一般的に、ビジネスシーンではPCやタブレット、プライベートではモバイルを利用することが多いため、BtoBの商材ではPCやタブレット向けの配信が中心となるようです。
- 地域・言語
- 市場に合わせて最適な地域や言語を選ぶことが重要です。日本向けの製品・サービスを提供している場合は、ターゲティングも日本・日本語が対象で問題ないでしょう。
他にも、OS(WindowsやMacなど、コンピュータを動作させるための基本システム)やブラウザ(Google ChromeやInternet Explorer、Mozilla Firefox、Apple Safariなど、インターネット上のWebページを閲覧するためのソフトウェア)、広告閲覧時間帯などによってもターゲティングすることができます。
このように、ユーザの環境によるターゲティングは、比較的おおまかなターゲットの絞り込みと言えそうです。
これらの条件は単独でも使うことができますが、組み合わせて利用することが多いようです。例えば「日本国内で、PC・タブレットを使っているユーザーに対して、平日の9時~18時に広告を配信する」とすれば、平日勤務しているビジネスユーザーがターゲットになりやすくなります。
ユーザ属性
ユーザの環境よりももう少し詳細にターゲティングしたい場合に利用される条件です。
会員情報やWeb上での閲覧履歴・購買行動などから、閲覧ユーザの年齢層・性別・興味関心などの条件で分類し、特定の条件に当てはまるユーザ層にのみ広告を配信することができます。
例えば、「30代の男性で車に興味がある」といったようなユーザ層に対して、中古車の購入を訴求するような広告を配信することも可能になるのです。
これらの属性は、Cookieと呼ばれる仕組みによってユーザのWeb上での行動履歴を収集したものから推定しています。「こういったサイトを見ているということは、おそらくこのユーザは男性/女性だろう」「よく車のサイトを見ているということは、興味があるのではないか」などの推定を重ね、ターゲティング可能なユーザ属性として提供されているのです。
また、この属性の中には、自社サイトへの訪問履歴なども含まれます。
「過去30日以内に自社サイトに訪問したユーザ」に対して購入を促進する広告を配信したり、逆に「これまで一度も自社サイトに訪問していないユーザ」に対して、自社ブランドを認知させる広告を配信するなども可能です。
これらの属性を組み合わせて「サイトに訪問したユーザと類似性の高いユーザ層」に対して広告を配信する、などもおこなえるのです。
いざ、DSP運用開始!おさえるべきポイントは?
DSPの仕組みやターゲティングについて理解ができたら、いよいよ運用です。ここでは、DSP広告を運用する上でおさえておきたいポイントをご紹介します。
DSPのタイプによって、運用の内容が変わってくる
DSPには大きく分けてアルゴリズム型と手動調整型の2種類があり、それぞれによって運用の幅が変わってきます。まずはタイプの違いを理解しましょう。
- アルゴリズム型DSP
- 目標となるCV数やCPAを設定したら、DSPに搭載されているアルゴリズムによって自動的に最適化してくれるタイプのDSPです。運用にそこまで工数がかからないことが魅力的ですが、思ったように成果が出ない時にも手動で調整できる幅が狭く、手動改善がしにくいというデメリットもあります。
- 手動調整型DSP
- ターゲティング設定だけではなく、入札価格なども含めた細かい調整を手動でおこなうタイプのDSPです。アルゴリズム型と比べて運用工数が大きくかかってしまいますが、その分手動による柔軟な調整を行えることがメリットです。
手動調整は影響度を考え、優先度を決めていく
手動調整は細かく柔軟な運用をできることがメリットですが、しっかりと優先度を決めて調整していかないと、「時間はかけていても効果が出ない」ということになりかねません。
時間は無限にあるわけではないため、かける時間と得られるインパクトによって調整の優先度を決めると良いでしょう。
改善項目によるインパクトの大きさは、以下の順であると言われています。
- ① ターゲティング
- ② 配信面(メディア)
- ③ バナークリエイティブ/LP(ランディングページ)
- ④ フリークエンシー設定
- ⑤ 時間帯配信/曜日配信等の設定
また合わせて、どの改善項目がどのように影響するかも考えておくことが重要でしょう。
例えばターゲティングの変更は、そもそも自社のWebサイトに集客するユーザ層自体が大きく変わってしまう可能性もありますが、曜日や時間帯の変更であれば、自社の広告にユーザが触れる際のマインドやモチベーションなど比較的小さな変化だと考えられます。
重用なのは「誰に、どのような訴求を、いつ見せるか」を設計したうえで、「どのポイントを改善するか」を考えながら調整を行うことでしょう。
DSP 運用のコツは?
最後に、DSPで成果を出すために押さえておきたい運用のポイントをご紹介します。
1.ゴールを明確に定める
その広告の目的がどこにあるか、はじめに定めておくとよいでしょう。
Webサイトでの資料請求なのか、ホワイトペーパーのダウンロードなのか、キャンペーンの告知なのか。 ここで定めたゴールによって、その手前に置くべきKPI(key performance indicatorの略。組織や業務の目標達成度合いを測る指標のうち、目標達成に大きく影響する重要な指標のこと)も変わってきます。
例えばWebサイト上での資料請求をゴールとして設定する場合には、その手前に置く指標は以下のようなものが挙げられます。
Webサイトへの流入数×資料請求に至る割合=獲得できる資料請求数
さらに細分化すれば、資料請求フォームへの遷移数や製品の機能・価格などといったページへの遷移数などを追うこともできるでしょう。
重要なのは、「目指すべき指標はなにか」「その指標を達成するために追うべき中間指標は何か」を明確にすることです。
2.必要に応じてマイクロコンバージョンを活用する
例えばゴールがWebサイト上での資料請求獲得だとしても、月間の平均資料請求数数が数件では、調整がうまくいっているかどうかがわかりにくいこともあるでしょう。
そこで役に立つのが、「マイクロコンバージョン」という考え方です。
マイクロコンバージョンとは、最終コンバージョンに至るまでの各段階に設定する中間コンバージョンのことです。例えば最終コンバージョンが資料請求であるとしたら、マイクロコンバージョンは資料請求フォームや価格・機能などのページへの遷移などが当たります。
これらの遷移をマイクロコンバージョンとしてカウントすることで、資料請求に近いユーザを集客できているかの参考指標にすることができます。
また、とくにアルゴリズム型のDSPでコンバージョン数最適化のアルゴリズムを用いる場合、基準となるコンバージョンの母数が多くなるためにより精度を高められるというメリットもあります。
ただし、マイクロコンバージョンのポイント設定を誤ってしまうと、最終コンバージョンから遠いユーザの集客につながってしまう可能性もあるため、注意が必要です。
さいごに
DSPの運用と聞くと、どうしてもハードルが高いと感じてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし重要なのは「自社のターゲットに対して、どれだけ適切な広告メッセージを訴求できるか」という点です。
おさえるべきポイントをしっかりと理解して、DSPの効果を最大化するような運用を目指しましょう!
これを読んでもっとUrumo!
この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。