単独セミナーと共催セミナー、それぞれの違いと押さえるべきポイント
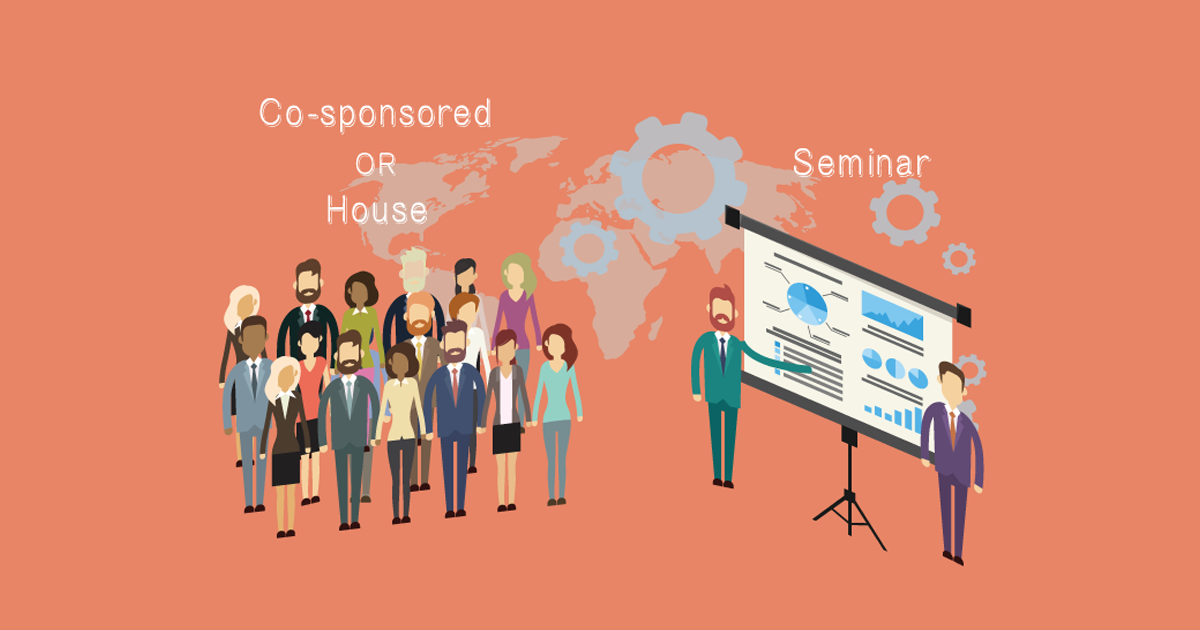
ここ数年、共催セミナーの注目度が高まっています。インターネットの発展でサービス同士が繋がったり、クラウド化の普及などによって他社ツールとの連携がしやすくなったりしていることで、関連する企業同士で協力してセミナーを開く機会が増えているようです。
話題性があり魅力的な共催セミナーがあちこちで開催されていますが、共催セミナーを開催してどんなメリットがあるのでしょうか?そこで今回は、自社セミナーと比較して、共催セミナーのメリット・デメリットを見ていきたいと思います。
何のためにセミナーを開催するの?
そもそも何のためにセミナーを開催するのでしょうか?自社セミナーと共催セミナーを比較する前に、セミナーを開催する目的を考えてみましょう。
- ・製品/サービスをまだ知らない人に認知してもらいたい
- ・セミナーを通して自社製品/サービスに対する興味度合いを高めてほしい
- ・興味をもっている人から直接意見や悩みを聞きたい
- ・既存顧客にもっと活用する方法を知ってほしい
以上のように、製品/サービスの認知度を高めたかったり営業リストを担保したかったりと、さまざまな理由でセミナーを開催しようと検討されているかと思います。つまり、「今必要としているモノ・コトは何なのか」を明確にした上で開催できると、セミナーの目的達成に近づくでしょう。
次章で、自社セミナーと共催セミナーのメリット・デメリットを解説しますが、セミナーを開催したい理由やその後達成したいことを思い描きながら読むと、どちらのセミナーが適しているのか検討しやすくなりますので、ぜひ考えてみてくださいね。
規模別!自社セミナーのメリット・デメリット
自社セミナーとは、業界にまつわる潮流やノウハウ、自社製品/サービスの紹介などを行う、自社主催のセミナーです。自社の社員が講師を務めることが多いですが、より専門性の高いコンサルタントを講師として呼び、業界の話やノウハウなどを講演してもらうこともあります。
共催セミナーと比べて、他社の関与が少ないセミナーになるので、利害関係などを気にせずに開催することができます。ただ、一口に自社セミナーと言っても、セミナーを開催する目的によって規模や会場、セミナー内容を変える必要があります。
そこで、ここからは規模別に、セミナー開催のメリット・デメリットを比べましょう。
① 大規模セミナー(定員:70名~)
大規模セミナーは、企業・製品/サービスのイメージを形成し信頼に繋げるブランディングや、新しい人に企業・製品/サービスを知ってもらって認知拡大しつつ、新規リード(個人情報)獲得の目的で実施することが多いです。
- ▼メリット
-
- ・一回の開催でたくさんのリードを獲得できる
- ・セミナープラットフォーム※などで新規集客ができれば、今まで認知されていなかった潜在層へ新しくアプローチできる
※セミナープラットフォーム:さまざまなセミナー開催情報を掲載しているWebサイトのこと
- ▼デメリット
-
- ・企業や既存リストの数によっては、既存リストに集客メールを配信するだけではなく、新たな集客方法を実施する必要があり負荷がかかる
- ・会場手配、配布資料の準備、集客管理、当日の会場運営など、準備に手間がかかる
② 中規模セミナー(定員:11~70名)
中規模セミナーは、大規模セミナーの目的だけではなく、過去に獲得したリードや準顕在層の育成という目的でも開催できます。大規模セミナーよりも人が少ない中で、参加者の興味度合いを高めていくのに適しています。
- ▼メリット
-
- ・過去に獲得したリードの中から興味度合いの高い人が分かる
- ・悩みを抱えている準顕在層の興味度合いを高めることができる
- ・新規リードを獲得し、潜在層にアプローチできる
- ▼デメリット
-
- ・目的を明確にしないと、新規リードと過去に獲得したリードや準顕在層の両方を追ってしまい、コンテンツがブレることがある
- ・過去に獲得したリードの集客と同時並行で、新規集客を行う必要がある
③ 小規模セミナー(定員:~10名)
小規模セミナーは、大規模・中規模セミナーとは違って、ニーズが顕在化している人を獲得したり、コミュニケーションをとって直接的な関係を築いたりする際に適しています。既存顧客が交流できる場としても活用できます。
- ▼メリット
-
- ・直接のやり取りを通して、悩みや本音など生の声を収集できる
- ・メルマガを活用して、顕在層にアプローチできる
- ▼デメリット
-
- ・顕在層を満足させるコンテンツでないと、他社へ流れてしまう可能性がある
- ・新規リード数が少ない
いかがでしょうか。自社セミナーでも規模や開催目的が違えば得られるメリットも異なることがご理解いただけたかと思います。ぜひこちらを参考にして、自社セミナーであればどの規模で何を目的とした開催が現在のマーケティング戦略・方針に合っているのか、考えてみてください。
共催セミナーのメリット・デメリット
共催セミナーとは、同業種の会社や協業している会社などと組んで、業界の流れやノウハウについて講演したり、それぞれの製品/サービスを紹介したりするセミナーです。
では、共催セミナーのメリット・デメリットを見てみましょう。
- ▼メリット
-
- ・お互いの既存顧客や、過去に獲得した個人情報を共有できる
- ・話題性から新規集客に繋がる
- ・セミナー内容が自社セミナーよりも深まる
- ・一度に複数の講演ができ参加者の満足度が高くなる
- ▼デメリット
-
- ・集客の目標達成へのプレッシャーがかかる
- ・セミナー開催後、アプローチ時期が共催先と重なり、お客様の比較検討が長期化する
- ・同時に他社の情報も耳にするため、自社の製品/サービスの印象が薄くなってしまう可能性がある
- ・開催準備、会場手配、配布資料の準備、集客管理、当日の会場運営など、実施に手間がかかる
よりよい共催セミナーにするために
共催セミナーのメリット・デメリットを確認できたところで、開催するならば気をつけておきたいポイントを最後に3つご紹介します。
① 共催先の選定
共催先を決めるには、以下の3点がポイントです。
- ・共催先の企業に集客力があるかどうか
- →共催しても、話題性がなかったり相手が集客に力を入れてくれなかったりすると、集客目標を達成することが難しくなるでしょう。
- ・既存顧客や過去に獲得したリードなどアプローチできるリストが被りすぎていないか
- →獲得できたリード情報が、すでに自社で保有しているリードであれば、アプローチできる数が減ってしまいます。
- ・受注に繋がったり、組み合わせて解決策を提案できたりと、提供するソリューションにシナジーがあるかどうか
- →自社の製品/サービスとの関連性が薄いと、アプローチしても受注に繋がらない可能性が高くなってしまいます。
②形式の選定
セミナーの開催形式は、大きく「オンライン」「オフライン」の二通りがあります。
- オンライン:
- リモートワークの普及がきっかけで、現在主流の形式。集客しやすいが、ながら聞きされるなどのデメリットがある。
- オフライン:
- 会場費がかかったり、集客が伸び悩むことが多いが、参加者とのインタラクティブなコミュニケーションが取りやすい。
以上のように、それぞれ良いところも悪いところもあるので、じっくり考える必要がありますね。
③ 個人情報保護方針の合意
個人情報の利用目的について、双方の個人情報保護方針を確認する必要があります。というのも、獲得したリードを活用してアプローチする際に、互いの個人情報保護法に齟齬があると、活用できないこともあるからです。例えば、共催先の個人情報の利用目的に、共催セミナー開催社と参加者情報を共有し合うことの旨が記載されていなければ、共催先のリードを自社で活用して営業することはできません。
共催セミナー開催前に、個人情報保護法に準拠して利用目的を通知することに対して、双方の合意を得るか記載文言を変更することを忘れないでください。
さいごに
いかがでしたでしょうか。自社セミナーか共催セミナーか、どちらのセミナーの方が多くのメリットがありそうか、判断できたでしょうか?
セミナー開催は、一気に新規リードを獲得できたり、より近い距離でコミュニケーションを取ることができたりと、有益な手法として知られています。ただ、目的が定まらないままに実施すると、実施前に思い描いていたような効果を得ることは難しくなってしまいます。この記事を参考にして検討し、より効果的なセミナーを実施してくださいね。
『BtoB企業向けセミナー開催のための実践ノウハウBook』もあるので、ぜひダウンロードして読んでみてください。
これを読んでもっとUrumo!
この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。






