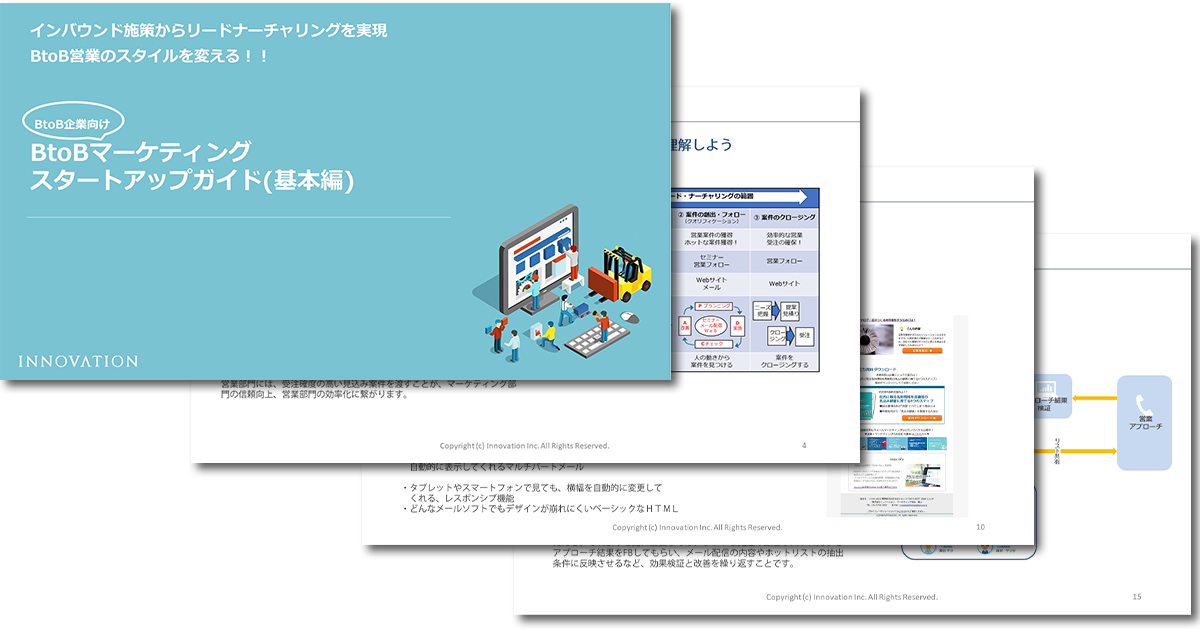ABM(アカウントベースドマーケティング)とは?導入のメリットや実践ステップを解説

近年「アカウントベースドマーケティング」というキーワードを耳にする機会が多くなってきた、という方も多くいるでしょう。アカウント(企業)を絞ってマーケティングを行う...と書いてみると、字面での解釈は難しくないですが、一体どのようなマーケティング手法を意図するものなのでしょうか。
今回は、「特定のリストへアプローチするテレマーケティングと違いは?」「なぜこのタイミングで注目され出したのか?」など今注目されているアカウントベースドマーケティングについて解説します。
ABM(アカウントベースドマーケティング)とは?
NTT PCコミュニケーションズの「用語解説辞典」によると下記のように説明されています。
企業が優良な顧客に対して、効果的にアプローチする手法のひとつ。アカウント・ベースド・マーケティング(Account-Based Marketing)を略して、ABM と表記することが多い。
この場合のアカウントは、顧客企業やクライアントといった意味と思っていい。そして、そのアカウント(企業)をよく知って、複数の部門が連携して適切なタイミングで適切な商談を行うことで案件の受注につなげる。おおむね、こういった営業活動を ABM といっている。
ここからもお分かりいただけるように「ABM」とは、幅広い顧客に対し均一に対応をするのではなく、売上が最大化する顧客(アカウント)を明確にし、戦略的に、組織的にアプローチをしていく手法を指します。
これまでの営業やマーケティングは、戦略的に業種や市場などの「ターゲット」を決めて活動を行っていましたが、ABMでは、より具体的な「企業や団体」を対象に活動を行うことがこれまでとの違いといえるでしょう。
1社当たりの売上が平均顧客単価の100倍もポテンシャルのある企業であれば、リソースが5倍10倍かかったとしても優先順位を上げて取り組む必要がある、という非常にシンプルで当たり前の考え方ですが、戦略的に取り組めている企業は多くないのが実態です。
直近の売上確保に目が向く中では忘れられがちですが、未来の大型顧客を創出するためには、マーケティング・営業が連携して、同じイメージの下で活動をおこなうことが求められています。
ABMが注目されている理由
ABM自体は新しい概念ではなく一般的な考え方ですが、再び注目されている背景には、名刺管理、SFA、MAツールといった、セールス/マーケ領域のテクノロジーの発達が寄与していると考えられます。
これまで、営業といえば属人的な活動が主流だったため、「交換した名刺は自分の机に保管」「ポテンシャルのあるクライアントは自分の勘と経験で見つける」というアナログなシーンが多かったものですが、ツールの登場によって、営業活動が大きく変化しました。
ABMとデマンドジェネレーションとの違い
比較して語られることも多い両者の違いについても見ていきましょう。
デマンドジェネレーションは、「リードジェネレーション(見込み顧客の新規獲得)」→「リードナーチャリング(獲得した見込み顧客の育成)」→「リードクオリフィケーション(育成により検討度合いが高まった顧客の選別)」という3つの一連の活動を経るマーケティング手法です。
このデマンドジェネレーションは、主にマーケティング部門が主体となり、あらかじめセグメント(市場・業種・従業員規模・役職など)された顧客(個人)に対して幅広くアプローチし、受注確度を高めていくことを目的としています。
対してABMはというと、売上の最大化を目的とし、あらかじめ対象となる企業を選定した上で、マーケティング部門と営業部門が一丸となり、様々な手段でアプローチを行う手法です。
このように、デマンドジェネレーションとABMは目的や対象が異なる手法ではありますが、対立する概念というわけではありません。デマンドジェネレーションで用いられる顧客管理や育成といったプロセスは、ABMを実施する上でも必要とされているのです。
ABMが向いている企業とは?
ABMは、全ての企業にとって効果的手法とはいえず、向いている企業があります。ABMは売上が最大化する企業(アカウント)を明確にし、戦略的に、組織的にアプローチをしていく手法であると解説しました。
このことから、一つのアカウントから多くの売り上げを獲得することが目的となります。つまり、ターゲットとする企業は中堅企業から、大規模レベルである必要があるといえます。
また、売上の最大化を目指す為には、自社で扱う商材が高単価であることや、アップセル・クロスセルが可能な複数の商材を持っていることも重要となります。
ABM導入のメリット
ここまでABM(アカウントベースドマーケティング)とは何かをご紹介しました。次にABMを導入することで得られる4つのメリットについて解説をしていきましょう。
ROIの向上
一つ目は、ABMに取り組むことでROIの向上が期待できます。先程も触れた通り、売上ポテンシャルが平均顧客単価の100倍の企業があれば、他の企業よりも10倍リソースを割いても十分すぎるほどのROIとなりますよね。このように、必要なところにコストを投下し無駄をなくすことで、これまで以上に効率的に成果を上げることができるためです。
リソースの無駄を減らせる
先ほども述べた通り、ABMでは、あらかじめアプローチ対象の企業を絞ります。そのため、無駄なコスト(ヒト・モノ・カネ)を特定の企業に集中できるため、無駄を減らすことができます。
PDCAを高速で回せる
少数の顧客をターゲットとするため、マーケティングや営業の仮説と実施、検証が容易になり、施策を高速で回していくことが可能になります。
営業とマーケティングの連携ができる
ABMを行うには、営業やマーケティング、開発などが同じ発想で成果を上げることが求められます。そのため、自社内で一貫したアプローチを行うことができます。
ABMのデメリット
ABM導入のメリットを確認しましたが、デメリットについても見ておきましょう。
上述したように、ABMには向いている企業と向いていない企業があります。一つのアカウントから多くの売り上げを獲得することが目的であるABMでは、クロスセルやアップセルなどで売上の最大化を目指します。そのため、自社で扱う商材が低単価であることや、アップセル・クロスセルが可能な複数の商材がない企業では、ABMを導入しても成果を上げにくいことがデメリットといえます。
また、絞り込んだ企業にのみアプローチを行うABMでは、一つのアカウントからの売上が大きいことが重要です。そのため、ターゲット企業は大手である必要があり、ターゲット企業の規模が小さいと思ったような成果を上げられないでしょう。
【4ステップ】ABMはどうやって実施する?
では、実際にどうやってアカウントベースドマーケティングを実践していくのでしょうか。以下の4つのステップに分けてご説明します。

1.アカウント(対象企業)を設定する
ABMを実施するには、まずは「自社にとって注力してアプローチするべき企業(アカウント)はどこか」を企業名レベルでリストアップするところから始まります。
上述の通り、多くのBtoB企業では、2割の顧客の売上が大半の売り上げを占めている状態が多いと思います。その2割の企業を企業規模・業種・地域などの属性から分析し、同じ属性で、かつ自社の既顧客ではないアカウントを選出します。
このアカウントリストを作成する上でもっとも手っ取り早い方法は、法人リストの購入です。帝国データバンクや東京商工リサーチ等が代表的な法人リストの販売を行っている企業ですが、中には下記のような特殊な切り口でリスト販売を行っている会社も存在します。
- ・新設法人
- ・海外進出企業
- ・ECサイト保有企業
- ・工場のCo2排出量
どこまでの情報を付与するかにも依存しますが、1リストの平均単価は50円程度です。仮に1,000社をアカウント対象としたとしても50,000円程度の予算で購入できるので、まずはこの企業リストを起点に、アカウントベースドマーケティングの戦略をつくっていきましょう。
ちなみに法人リスト提供企業ランドスケイプ社(リンク)という、データベースマーケティング支援会社は、累計1,200万件の膨大な法人リスト情報に加え、非常に細かな抽出条件でのリスト作成が可能です。
2.コンタクトポイントの有無の確認
次に対象となったアカウント内の意思決定者とのコンタクトポイントの有無を確認します。コンタクトポイントがあれば直接的なアプローチが可能ですが、なければコンタクトポイントを発掘する手段から検討する必要があります。
また、BtoB商材の場合は、サービス導入に際し意思決定に関わる人が複数人存在するケースが多いためアカウント企業の意思決定者が何人いて、どの部署に存在しているのかをイメージしておくことも、この段階で必要です。
3.コンタクトポイントの創出
コンタクトポイントがない場合、アプローチできるコンタクトポイントを創出する必要があります。展示会での名刺獲得や、コールドコールでの意思決定者発掘などが一般的な手段になります。
これまではこのようなダイレクトマーケティングが一般的でしたが、最近ではアカウント攻略に不向きとされていたWebマーケティングでのアプローチ手法も増加しており、IPアドレスで対象企業へのみバナーを配信する広告や、Facebook広告などがこれに該当します。Web広告によって認知を拡大し、ダイレクトマーケティングで刈り取りを行うなど、複合的に施策を組み合わせることも検討していきましょう。
また、獲得した意思決定者の情報はSFAやマーケティングオートメーションツール(MAツール)に取り込み、アプローチの素地を整えましょう。
ここで、アカウントベースドマーケティングに向いている広告のターゲティング方法をいくつかご紹介いたします。
・IPターゲティング
特定の企業IPのみを指定してアドネットワーク上に広告を配信する仕組みで、設定したアカウント企業のみに広告配信することが可能です。自社サービスの訴求のみならず、例えば同業他社でのよい成功事例を前面に訴求することで、対象アカウントからインバウンドでキーマン情報を取得することが可能です。
・職業、役職ターゲティング
クッキー情報を活用して、職業・職種や職位までターゲティングして広告配信をすることが可能なサービスも存在します。
- SniperAd
- 特定の医療職種だけに配信できる、ディスプレイ広告。例えば医師や薬剤師のみをターゲットにした広告配信が可能です。
提供元:株式会社リンクフォース
- SphereR
- 約4,800万人の就業対象者のWebサイト上の行動履歴/ステータス情報をもとにしたディスプレイ広告。職種や職業でセグメントすることが可能です。
提供元:マーべリック株式会社
4.アプローチ開始!
コンタクトポイントの整備・創出ができたら、いよいよアプローチ開始です。ABMでは直接的なアプローチによって、接触頻度を高めることが求められます。具体的にはインサイドセールスによる電話・メールや、場合によってはフィールドセールスによる商談を重ねても良いかも知れません。
また、MAツールを活用し、メールマーケティングやセミナー集客によって購買意欲の向上を図る、いわゆるナーチャリング活動もこのタイミングで必要な手段です。
ABMで活用できる3つのツール
ここでは、ABMの導入の際に欠かせない3つの主なツールについて見ていきましょう。
名刺管理ツール
営業個人が机の中にしまい込んでいた名刺をすべて一元管理し、企業の情報資産として取り扱うことができるようになりました。各部門の営業担当が、クライアント企業の誰と会ったか、また、逆にコンタクトポイントの無い部門はどこかなど、ターゲット企業に対して組織的なアプローチをしていくための土台作りを効率的に行うことができます。
SFA/CRM
名刺管理では主にコンタクトポイントの整理が役割でしたが、SFAやCRMの役割は、「各企業へのアプローチ可視化」です。いつ、誰が、誰と、どのような会話をしたか。また、各商談はどのようなフェーズになっているかといった営業活動の状況や、すでに取引が発生している場合はその取引額、サービスの継続状況など、商談発生→受発注→継続取引を全社的に一元管理することができるようになります。
MAツール(マーケティングオートメーション)
時代の変化によって、顧客との初回接触が、飛び込み・コールドコールなどのアナログな営業活動から、Webを中心としたリード獲得に移ってきていますが、そのリード情報を一元管理し、企業ごとの見込み度合い把握に活用できるのがMAツールです。
通常、リード情報として登録される際は、フォームへの入力などユーザーによる能動的な情報入力がきっかけになることが多くありますが、それによって(株)などの略語や、アルファベット⇔カタカナの混在など、様々な表記ゆれが存在しうるものです。MAツールには、各リードの表記ゆれを、企業ごとに紐付け、整理する機能が備わっています。また、企業名から、業種や売上/従業員規模といった企業属性を付与することもできます。
こういった機能を活用することで、各企業のポテンシャルを正しく把握し、対象アカウントの整理を効率化することができます。
さいごに
いかがでしたでしょうか?ABM(アカウントベースドマーケティング)自体は皆様のマーケティング活動の中でも、ごく自然に行われている考え方ではないでしょうか。実行のプロセスについても解説しましたが、より大切なのは自社の売り上げのコアとなりえる企業へのアプローチへはリソースを割いてでもアプローチするべきである、という考え方を関係者全員で共有することにあると思います。
今一度自社の顧客分析から、アカウント選定を見直してみましょう!