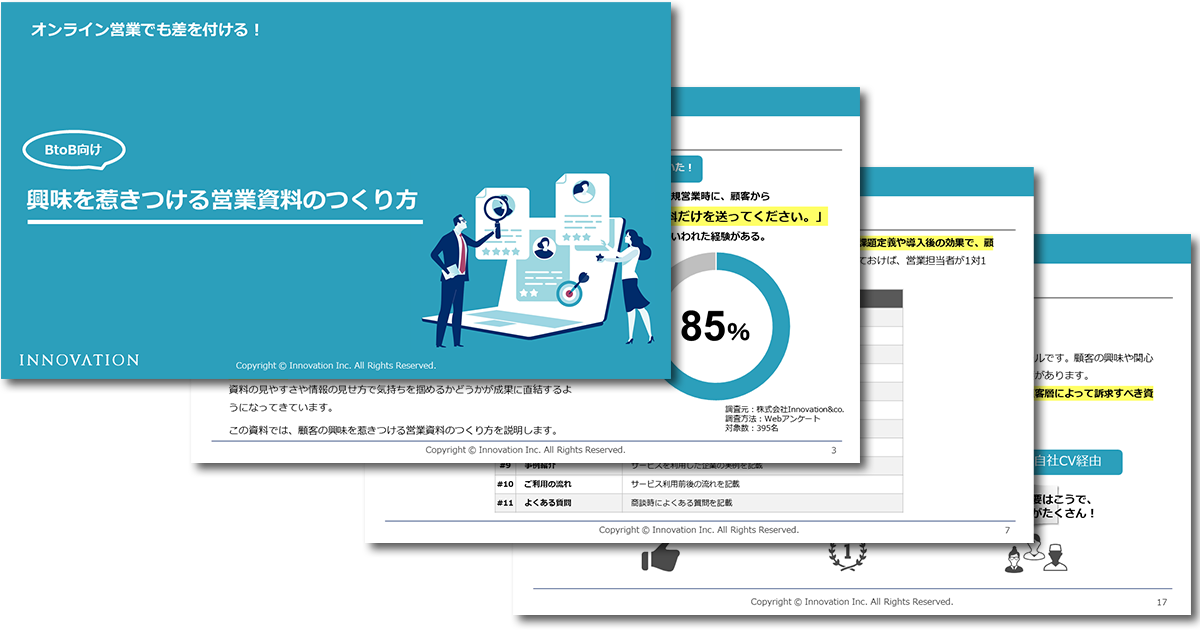営業資料の作り方完全ガイド!構成・デザイン・注意点も解説
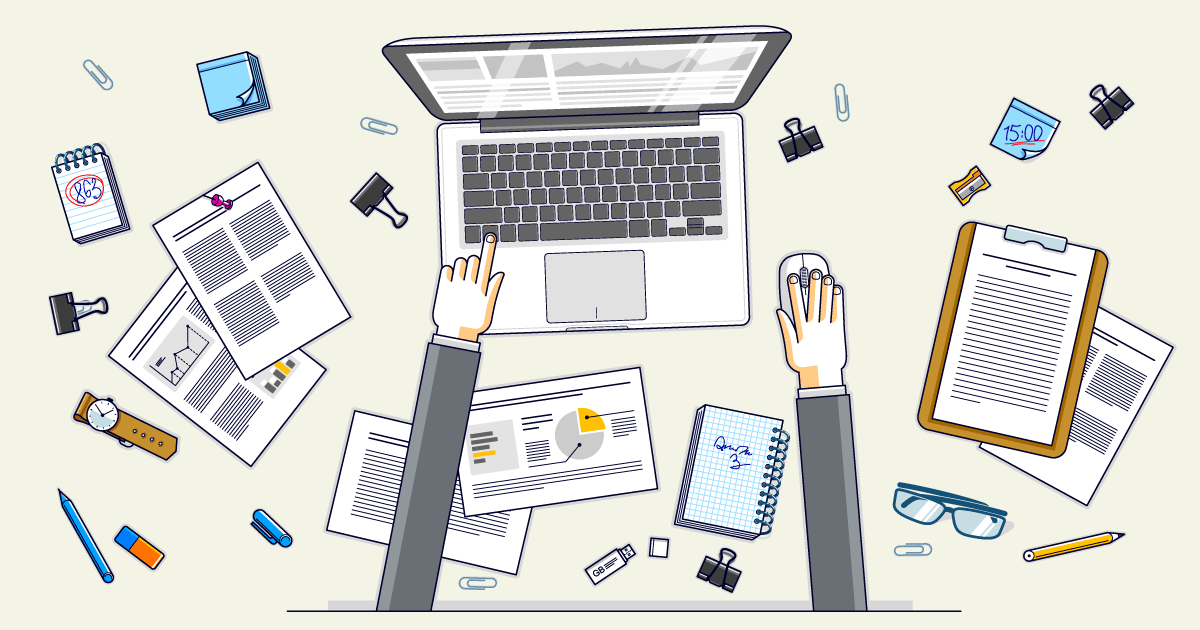
商談の際に、口頭だけでは難しい商品説明も、自社の商品やサービスの情報をまとめた営業資料があることで、より効果的に商談を進めることができます。また、市場の変化に伴い、オフラインで行う対面営業でなくオンラインでの営業活動を行うことが主流となってきており、これまで以上に営業資料が重要視されるようになりました。
この記事では、成果につながる営業資料を作るための構成テンプレート・作成のコツ・デザインの注意点・おすすめツールまで解説していきます。
- ▼この記事でわかること
- ・営業資料が重要とされる理由
- ・読まれる営業資料を作るための構成テンプレート
- ・作成時に意識すべきポイントとデザイン面での注意点
- ・営業資料作成に便利なツール3選
【無料ダウンロード】すぐに使える営業資料の作り方Tips
営業資料の役割とは?重要視される3つの理由
営業資料とは、顧客に対して商品・サービスの内容や価値、導入メリットを伝えるための「提案用ドキュメント」です。スライド形式やPDF資料として活用されることが多く、営業活動を支える重要な要素です。
近年では営業プロセスのオンライン化が進み、対面でのトーク力だけでなく「資料の完成度そのもの」が、商談の成否に直結するようになっています。
以下に、重要視される理由を詳しく見ていきましょう。
オンライン営業の効果を高められる
オンライン商談では、対面と比べて空気感や感情のやり取りが難しくなります。そこで重要になるのが、視覚的にわかりやすく、論理的に構成された営業資料です。
特に、課題→解決策→導入メリットという流れが整理された資料は、相手に信頼感を与え、次回アクションやクロージングといった商談のゴールにつながりやすくなります。
属人化の防止につながる
営業資料をきちんと整備しておくことは、「誰が説明しても伝わる」状態を作ることでもあります。属人化を避け、営業チーム全体で提案の質を均一化・再現性を高めるためにも、資料の型化や共有が欠かせません。
また、新人教育や引き継ぎの際にも営業資料があると、スムーズかつ効率的に情報を共有することができます。
社内検討の際も活用される
顧客が社内で意思決定を行う際、営業担当者は同席できません。だからこそ、提案内容を「資料だけで伝えられる状態」にしておくことが重要です。
営業資料は、顧客の社内稟議・比較検討の場でも活用されるため、決裁者や他部署を意識した構成やデザインが求められます。
営業資料の作成前に押さえておきたい3つの準備
営業資料の質は、作り始める前の準備で大きく差が出ます。やみくもにスライドを並べるのではなく、誰に・どのような場面で・何を伝えるかを明確にすることで、説得力のある資料に仕上がります。以下の3点は、必ず押さえておきたい準備項目です。
1.ターゲットを想定する
営業資料は「誰に向けて作るか」で構成も表現も大きく変わります。たとえば、サービス利用者向けと意思決定者向けでは、重視すべきポイントが異なります。業種・職種・決裁権の有無など、ターゲットの立場や関心を明確にすることが第一歩です。
2.利用シーンを想定する
その資料は「どんな商談の場面」で使うものか?初回訪問・比較検討中・価格交渉など、利用シーンによって資料の役割は変わります。商談フェーズに合った訴求ができるよう、使用場面を想定して内容を調整しましょう。
3.利用シーンに合わせた構成を考える
ターゲットと利用シーンが定まったら、それに適した構成を考えます。たとえば、初回提案では「課題の整理」や「導入メリット」の説明が重要ですが、価格交渉の場面では「費用対効果」や「導入ステップ」の明示が必要です。相手に合わせて構成を最適化することが、伝わる資料づくりの鍵となります。
【12ステップで解説】営業資料の基本構成
営業資料は、顧客の関心を引きつけながら、自然な流れで情報を伝える構成が理想です。以下は、実際の商談で使いやすい基本の12ステップ構成です。状況に応じて追加や削除しつつ、ベースとして活用できます。
- 表紙
- 商品・サービス概要
- よくある課題
- サービス紹介
- 他社との比較表
- 導入メリット
- 導入企業の事例紹介
- 料金プラン・費用感
- 導入手順
- よくある質問(FAQ)
- 会社概要
- 問い合わせ先(CTA)
1.表紙
資料タイトル・会社名・ロゴなどを記載。商談名や日付を入れるとより丁寧な印象です。
- 【目的】
- 資料の第一印象を決定づける導入部分。
- 【内容例】
- ・「〇〇業界向け 業務効率化ツールご提案資料」
- ・自社ロゴ、商談日、担当者名
ポイント:タイトルは課題解決を想起させるワードにすると効果的。
2.商品・サービス概要
提供している製品・サービスの基本情報を簡潔に紹介します。
- 【目的】
- 提供するサービスを一言で理解してもらう。
- 【内容例】
- ・サービス名と短いキャッチコピー
- ・代表的な機能3〜4つ
- ・提供形態(SaaS、導入型など)
ポイント:ロゴ・スクリーンショットや図解を添えると視認性アップ。
3.よくある課題
顧客が抱えやすい悩みや課題を提示します。課題への共感が、次の提案内容の説得力を高めます。
- 【目的】
- 顧客の「共感」を得る。
- 【内容例】
- ・「Excel管理が煩雑でミスが多発」
- ・「属人化が進み、業務の標準化が難しい」
- ・「営業活動の状況が見えづらい」
ポイント:「あるある」と思わせる内容がベスト。業種ごとにカスタマイズするのが理想。
4.サービス紹介(課題解決の方法)
課題解決にどう貢献できるかを具体的に解説します。機能や特徴を伝えるページです。
- 【目的】
- 前ページの課題に対する解決策を提示する。
- 【内容例】
- ・「ワンクリックで進捗管理が可能」
- ・「自動レポート機能で属人化を防止」
- ・「SFA連携で営業活動の見える化」
ポイント:「Before/After」形式や機能別に整理すると伝わりやすい。
5.他社との比較表
競合製品との違いを明確に伝えることで、自社の強みや独自性を際立たせます。
- 【目的】
- 自社サービスの強みを客観的にアピール。
- 【内容例】
- ・導入スピード
- ・サポート体制
- ・コストパフォーマンス
ポイント:表形式で視覚的に示すのが基本。強みは色やアイコンで明示すると良い。
6.導入メリット(成果・効果)
作業時間の短縮、コスト削減、CV率向上など、定量・定性的に導入メリットを提示します。
- 【目的】
- 導入後の「成果」をイメージさせる。
- 【内容例】
- ・「業務時間を月〇時間削減」
- ・「商談化率が1.5倍に」
- ・「社内稟議のスピードが2倍に」
ポイント:定量データがあると信頼度アップ。
7.導入企業の事例紹介
実際の導入企業や活用事例を紹介することで、信頼感・安心感を与えます。
- 【目的】
- 信頼感・実績を訴求する。
- 【内容例】
- ・導入企業のロゴ掲載
- ・業種・課題・導入効果を紹介
- ・実名または匿名でもOK
ポイント:ストーリー形式(課題→施策→効果)で語ると読みやすい。
8.料金プラン・費用感
価格帯やプラン構成を明示します。可能であれば参考価格や初期費用なども加えると親切です。
- 【目的】
- 顧客の「費用に対する不安」を解消し、意思決定を後押しする。
- 【内容例】
- ・初期費用・月額費用・プラン別料金表
- ・オプション有無/最低契約期間
- ・「〇名までは無料トライアル可」などの訴求も効果的
ポイント:価格だけでなく「費用対効果」を補足すると、説得力が高まる。
9.導入手順
契約から利用開始までの流れを説明。「いつから使えるか」が明確になります。
- 【目的】
- 導入ハードルを下げ、「スムーズに始められる」印象を与える。
- 【内容例】
- ヒアリング
- ご契約
- キックオフミーティング
- 初期設定・操作研修
- 利用開始・伴走支援
ポイント:フロー図やタイムライン形式にすると、視覚的にも理解しやすい。
10.よくある質問(FAQ)
導入前に懸念されやすい点をあらかじめ解消しておくことで、商談の不安を軽減できます。
- 【目的】
- よくある不安・懸念を事前に解消し、商談の「つまずき」を減らす。
- 【内容例】
- Q. 最短利用開始はいつですか?
- Q. 社内にIT担当者がいなくても大丈夫?
- Q. 最低利用期間はありますか? など
ポイント:営業現場でよく聞かれる質問を元に作る。
11.会社概要
信頼性を補強するために、企業情報や実績・所在地などを掲載します。
- 【目的】
- 信頼性を高め、「安心して取引できる企業」であることを伝える。
- 【内容例】
- ・会社名、設立年、所在地
- ・代表者名、社員数、事業内容
- ・拠点情報・グループ会社など
ポイント:簡潔にまとめ、信頼感を与えるデザインで仕上げる。
12.問い合わせ先(CTA)
次のアクション(連絡・資料請求・デモ依頼など)につながるよう、明確なCTAを配置しましょう。
- 【目的】
- 商談の次のアクションを明確に示し、リードや商談につなげる。
- 【内容例】
- ・担当者名・電話番号・メールアドレス
- ・お問い合わせフォームやQRコード
- ・「無料デモ予約はこちら」などCTA
ポイント:「いつまでに」「何をしてほしいのか」が明確だと、反応率アップ。
この12ステップはあくまでベースですが、読み手の職種・商談フェーズ・情報リテラシーによって、順番を入れ替えたり、省略したりする調整も有効です。重要なのは、「知りたい順番で」「必要な情報が過不足なく入っていること」です。それが、成果につながる営業資料作成のコツとなります。
伝わる営業資料にする3つのコツ
営業資料は、単に情報を並べただけでは伝わりません。限られた商談時間の中で、相手に「理解してもらい、行動してもらう」ためには、伝え方に工夫が必要です。ここでは、営業資料をより効果的にするための3つの作成ポイントをご紹介します。
1.簡潔にまとめ、ひと目で内容が伝わるようにする
営業資料では、「一目で何を伝えたいか」がわかることが非常に重要です。長文や詰め込みすぎた情報は読み手の集中力を奪い、要点が埋もれてしまいます。
そのため、1スライドにつき1メッセージを基本とし、見出し・ビジュアル・箇条書きを使って情報を整理しましょう。さらに、専門用語の多用は避け、誰でも理解できる表現を心がけることもポイントです。
2.疑問や不安を先回りして解消する
営業資料では、自社の強みやサービスの説明をするだけでなく、顧客が不安に感じそうなポイントをあらかじめカバーしておくことが大切です。たとえば、「本当に効果が出るのか?」「導入に時間がかかるのでは?」「他社と何が違うのか?」といった懸念を予測し、比較表・事例・FAQ・サポート体制などのコンテンツで信頼性を補完しましょう。
先回りして不安を解消できる営業資料は、商談の障壁を下げ、顧客の意思決定を加速させる力を持ちます。
3.数字やデータを用いて具体性と説得力を高める
営業資料において、「業務効率が向上します」といった定性的な表現だけでは、読み手にとっては説得力に欠けることがあります。そのため、数値・グラフ・事実ベースのデータを積極的に盛り込むことで、具体的なイメージや導入後の効果が明確になります。
たとえば「業務時間を月30時間削減」「導入企業の継続率95%」などの数字は、読み手に安心感と納得感を与えます。特に意思決定層にとっては、定量的な裏付けが重要な判断材料となります。
営業資料を見やすく整えるデザインの工夫
営業資料は内容だけでなく、「どう見せるか」も非常に重要です。特にオンライン商談が増えている今、視認性・印象・読みやすさを意識したデザインが成果に直結します。以下の3つのポイントを意識しましょう。
1ページにつき1メッセージに絞る
スライド1枚に複数の情報を詰め込んでしまうと、読み手が「結局何が言いたいのか」が分からなくなり、内容が記憶に残りません。そのため、1ページにつき伝えるべきことを1つに絞ることが重要です。
たとえば、「導入効果」のページなら、そこでは効果のインパクトだけに集中させ、料金や事例などは別ページに分けるようにしましょう。伝えたいことを明確にし、情報の整理されたスライドは、読み手の理解と記憶に残りやすくなります。
見やすいフォントや文字サイズを設定する
営業資料は、特にオンライン商談において「画面越しでどう見えるか」が重要です。文字が小さい、書体が細すぎる、コントラストが弱いといった資料は、相手にストレスを与え、集中力を削ぐ原因になります。
背景とのコントラストも意識し、白背景×黒・紺など、読みやすさを最優先に設計しましょう。
使用するカラーは3色までに抑える
配色が多すぎる資料は、統一感がなくチープな印象を与えがちです。デザインに慣れていない場合は特に、カラーは「ベース・アクセント・強調色」の3色に抑えるのが無難です。たとえば、
- ・ベース:白
- ・文字色:黒 or グレー
- ・アクセント:ブランドカラーやブルー系など
という構成にすると、清潔感・信頼感・視認性をバランスよく保てます。図解やグラフの色もこのルールに合わせると、一体感のある資料に仕上がります。
営業資料作成で失敗しないための注意点
ここでは、作成時に意識すべき3つの注意点を紹介します。
読み手に寄り添った資料にする
営業資料は「自社の言いたいこと」を伝えるものではなく、「相手が知りたいこと・不安に思っていること」を解消するためのものです。そのためには、読み手の立場・業種・職種・導入フェーズなどを理解し、「自分ごと化」しやすい言葉や事例、表現を選ぶことが大切です。
たとえば、ITリテラシーの高くない相手に専門用語を並べると逆効果ですし、決裁権のない担当者にコストの話ばかりしても響きません。相手の視点に立って内容を確認することが重要です。
必要な情報が不足していないかをチェックする
商談が進まない原因の一つに「資料に情報が足りない」ことがあります。特に以下のような情報が不足しがちです。
- ・具体的な導入効果
- ・導入までの手順
- ・サポート体制
- ・よくある質問
- ・比較検討時に必要な差別化要素 など
資料を完成させたら、「この資料だけで社内で稟議を通せるか?」という視点で見直すことが重要です。第三者チェックや営業メンバーとの確認も行いましょう。
顧客に合わせて複数の資料を作成する
一つの資料で全ての顧客に対応しようとすると、情報が冗長になったり、誰にも刺さらない資料になる可能性があります。顧客の業界・課題・検討フェーズに応じて、内容・構成・強調ポイントをカスタマイズした資料を複数用意するのがベストです。たとえば、
- ・初回提案用資料
- ・機能紹介に特化した補足資料
- ・費用感にフォーカスした資料
- ・導入事例・サポート体制中心の資料
などを使い分けることで、より相手にフィットした提案が可能になります。
営業資料を効率よく作るための方法3選
ここでは、営業資料を効率よく作るための方法をご紹介します。用途や使い勝手に応じて、最適なものを選びましょう。
1.PowerPoint
PowerPoint(パワーポイント)は、最も広く利用されているプレゼンテーション作成ツールの一つです。テンプレートや図表機能が充実しており、提案書やプレゼン資料、PDF納品資料など、幅広い営業用途に対応できます。
- 主な特徴
- ・オフラインでも使用できる安定性
- ・資料の印刷やPDF出力に強い
- ・高度なアニメーションやスライド演出も可能
2.Google スライド
Google スライドは、Googleアカウントがあれば無料で使えるクラウド型の資料作成ツールです。複数人で同時に編集できるため、営業やマーケティングなどの部署横断での資料作成する場合にも便利です。
- 主な特徴
- ・URL共有で資料展開がスムーズ
- ・リアルタイム編集・コメント機能あり
- ・スマホやタブレットでも閲覧しやすい
3.Canva
Canva(キャンバ)は、ブラウザ上で動作するオンラインデザインツールです。営業資料や提案書向けのテンプレートが豊富で、デザインが苦手な人でも見映えの良い資料が簡単に作成できます。
- 主な特徴
- ・無料プランでもテンプレートが充実
- ・直感的な操作で編集可能
- ・画像やアイコン素材も豊富に用意されている
まとめ
営業資料は単なる説明ツールではなく、商談の成否を左右する戦略的なツールです。作成前の準備から構成設計、デザイン、活用ツールの選定まで、丁寧に設計することで、相手の理解と納得を引き出しやすくなります。
資料の完成度は、そのまま営業活動の成果に直結します。ぜひこの記事を参考に、自社の価値を最大限に伝える資料づくりに取り組んでみてください。