知らないと恥をかく!?「売上高」「営業利益」「純利益」の違い
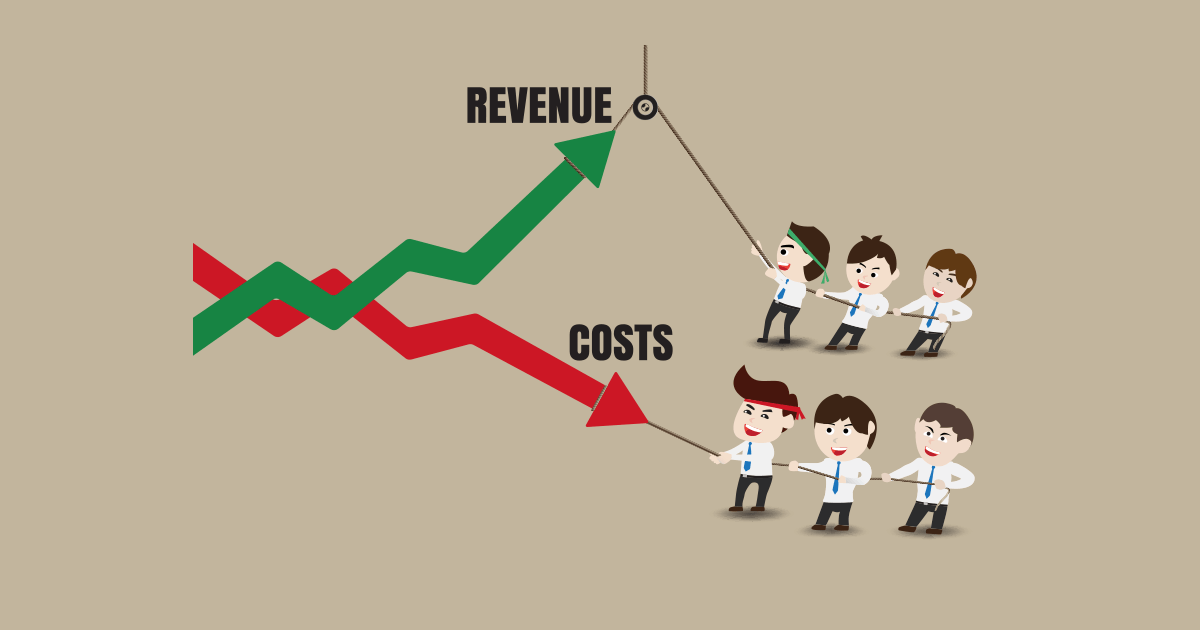
営業パーソンといえども、自分が担当する商品やサービスだけを売っているだけでいいというわけではありません。近年では、経営的観点を備えたうえで、自身の担当する商品の販売を進めていくことが求められています。
最もシンプルな経営的観点といえば、「損益はどのようになっているか?」ということです。相手の課題が「売上を上げたい」のか「利益を上げたい」のかによって、考えるべきポイントも変わってきます。
ここでは、いまさら聞けない損益項目について、詳しく解説します。
売上高とは?
売上高というのは、企業が商品やサービスを顧客に提供した際に計上するものをいいます。
つまり、主たる営業活動によって得た販売額のことを指すのです。営業パーソンとしては、この項目はよくわかることでしょう。営業活動をして、商品やサービスを提供した際に、その対価として受け取ったお金が「売上高」となります。自分ががんばった分だけ、この項目の数値がどんどん増えていくのです。
通常、売上高と呼びますが、シンプルに売上と呼称されることも少なくありません。企業によっては、その中で、商品売上高・製品売上高などに分類されることがあります。商品売上高というのは、自社で製造したものではなく、外部から仕入れて販売した売上のことです。
一方で、製品売上高は自社で製造や製作したものを販売した場合の売上のことをいいます。利益の元手となるものなので、売上高は多ければ多いほどよいとされています。たとえば、前年などと比較して、少なくなっている場合は、原因を特定したうえで、なんらかの対策が必要となるでしょう。
営業利益とは?
営業利益とは、販売した商品の「売上高」から「売上にかかったコスト」を差し引いた残りのもののことを指します。つまり、営業で得たもうけともいえるでしょう。
売上にかかったコストというのは、「商品」の場合、その商品を仕入れするために支払った仕入費用です。また、「製品」の場合は、製造するためにかかった人件費や光熱費などの費用のことをいいます。 さらに、営業パーソンの人件費や、顧客の所に出向くために使った交通費や旅費、そして光熱費や備品なども含まれます。
これらすべてのコストを差し引いて残ったものが利益となるのです。売上よりも、コストが多くなってしまうと、赤字となり何も残りません。そのため、企業としては、売上高を上げつつ、できるだけコストを削減することで、利益を確保することができるのです。
なお、もし赤字になった場合は、営業利益ではなく、営業損失と呼ばれます。営業利益で黒字になっているのであれば、本業での利益はしっかり確保できていると判断することができるでしょう。
純利益とは?
純利益とは、営業利益とはまた異なる利益の指標です。
営業利益というのは、企業の本業の仕事によって発生したコストを売上高から差し引いた金額です。一方で、純利益というのは本業で発生した営業利益から、営業外損益、特別損益などの本業以外の費用を差し引いた利益となります。つまり、銀行からの借入利息や、海外取引による為替差損益、そして固定資産の除売却による特別損失などがそれに当たります。
ここまでで得た利益から、企業の法人税や住民税、事業税などを差し引いたものが純利益です。ここで生まれた利益が、最終的な企業の利益となっており、企業はこの利益を使って、次年度以降の営業を行ったり、事業規模拡大をするための投資に使ったりするのです。
なお、営業利益がプラスであったとしても、借入利息が多かったり、災害などの要因で損失が増えたりすると、最終的に赤字になってしまうことがあります。また、逆に営業損失になっていたとしても、保有有価証券などを売却によって、最終的には黒字転換することも少なくありません。ちなみに、利息や為替差損益などの、営業外損益を差し引いた利益を「経常利益」と呼びます。
トータルで判断をする
自社や取引先の売上高や利益を分析する場合には、ここでご紹介したような項目それぞれを見るのではなく、広い目線で判断する必要があります。どれだけ売上が多くても、コストをかけすぎてしまうと、最終的に損失を出してしまう恐れがあるでしょう。逆に売上が低かったとしても、ほとんどコストがかかっていないのであれば、大きな利益となる可能性もあるのです。
また、財務分析は、1年だけの売上高や利益だけを分析するものではありません。「前年度とはどのような変化があるのか」「ここ3~5年で目に見えるような変化はあるのか」などを分析すると、企業の経理的な傾向を知ることができるでしょう。ちなみに、現在進行形で進んでいる会計期間の利益を「当期純利益」と呼びます。
まとめ
売上高や利益を知ることで、「自社の経営状況はどのくらいなのか」「さらに発展するためには、何を意識していけばいいのか」を知ることができるようになります。また、新規取引先と契約を結ぶ場合に過去の利益を分析すれば、「安心して取引ができる会社か」などの与信の判断材料となることでしょう。
これらの情報が載っている「損益計算書」は、慣れていないと、最初は読むのも嫌になってしまうかもしれませんが、実はそこまで難しいものではありません。ぜひ、皆さんもこれらの数字を分析してみてはいかがでしょうか。
これを読んでもっとUrumo!
この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。






