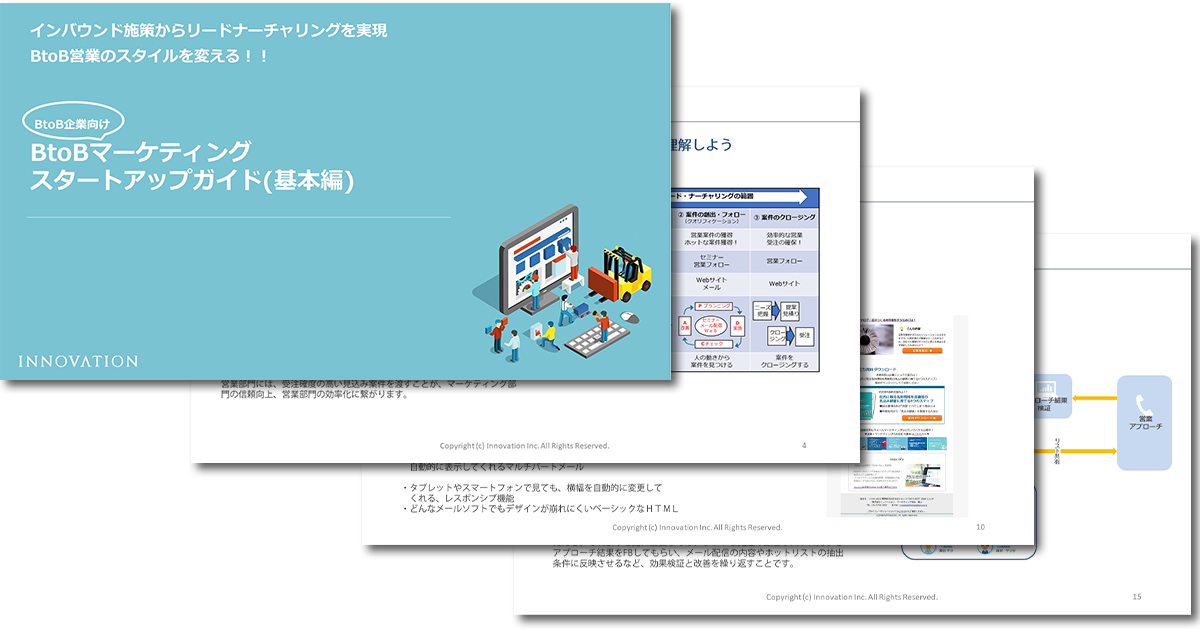これから始めるBtoBマーケティング~基本編~

近年、続々と新しいマーケティング施策や概念が出てきていて、いざマーケティングを始めようとしても、結局何を実施すれば良いか悩まれる方も多いのではないでしょうか。 今回は、マーケティングに力を入れ始めた企業向けに、改めてBtoBマーケティングの基本や、検討すべき5つの施策をピックアップしてご紹介したいと思います。
もちろん「何がベストか」は企業によって異なるとは思いますが、「マーケティングに力を入れていきたいが何から始めればいいのか分からない」とお悩みの方のお力になれれば幸いです。
BtoBマーケティングとは?
BtoBマーケティングとは、企業対企業に特化したマーケティングのことで、ユーザーにとって有益な情報を配信し、売上につなげる施策やコミュニケーションを図るプロセスのことです。ここでは、そのBtoBマーケティングが注目されている理由と、BtoCマーケティングとの違いについてご紹介します。
注目されている理由
これまでの営業活動は、飛び込みやテレアポなどで担当者が足で稼ぐものとされており、顧客側も製品の導入検討をする際には、定期的に訪れる営業担当者に相談するのが一般的でした。しかし、インターネットの普及により、顧客自身が商品やサービスについての情報収集を簡単に行えるようになり、実際に企業に問い合わせが入る頃には、顧客は粗方の導入検討を終了していることも多くなりました。
また製品がSaaSやクラウドサービスなどのサブスクリプション型へと切り替わったことで、サービス移行へのハードルが下がり、一度購入したからといって顧客を囲い込むことが難しくなりました。
こうした市場の環境下でも自社を選んでもらうために、早い段階で顧客に接触し、顧客の見込み度合いを高めていくことや、顧客と継続的に接点を持ち続け、信頼関係を築くためのBtoBマーケティングが重要となっているのです。
BtoCとの違い
BtoBとは「Business to Business」を略したもので、法人向けのビジネスモデルのことを表します。対して、BtoCとは「Business to Consumer」の略で、個人消費者を対象とします。このようにターゲットが異なることがBtoBマーケティングとBtoCマーケティングの最大の違いといえます。
以下の表で比較してみましょう。
| BtoB | BtoC | |
|---|---|---|
| 対象顧客 | 法人 | 個人 |
| 顧客数 | 多い | 少ない |
| 単価 | 高額 | 少額 |
| 取引回数 | 少ない | 多い |
| 購入決定者 | 決裁権限者 | 購入者本人 |
| 検討期間 | 中長期的 | 短期 |
| 購入目的 | 組織としての利益 | 個人の利益 |
この表から、BtoBとBtoCでは購入決定者や検討期間が異なることがわかります。詳しく見ていきましょう。
- ・購入決定者の違い
- BtoBの場合、商品の購入には担当者と決裁者が異なる場合がほとんどです。担当者が商品についてリサーチし、決裁者が認可をして初めて購入が決定されます。
一方BtoCの場合、担当者と決裁者が同じです。個人の買い物なので、どんな商品を選ぶのか、また実際に購入するのかも自分で決められます。
- ・検討期間の違い
- BtoBとBtoCは購買行動の違いにより、検討期間も大きく異なります。
BtoBは担当者と決裁者が違うため、部門や役職を巻き込んで検討し、最終的には社内稟議を通す必要があり、成約までに数ヶ月〜1年かかることが多くなります。
一方のBtoCは、車や家などの一部高額商品を除き、基本的には一人で決められるため、店頭で見たり、ネット広告で見かけたから買うといった行動になります。購買まで一瞬〜数日と検討期間が短いのです。
BtoBマーケティングの一般的なプロセス
では、実際にBtoBマーケティングではどのようなプロセスがあるのでしょう。ここでは具体的なマーケティングプロセスについて解説します。
1.顧客ニーズの把握
マーケティングを始める際には、顧客理解を深めることが重要となります。顧客に寄り添い、課題やニーズを把握することが顧客の求める商品を作ることにつながるのです。
2.リードジェネレーション(見込み顧客獲得)
顧客のニーズを把握し、課題解決につながる製品を作ることができたら、次にその製品を購入してもらえそうな見込み顧客にアプローチするリードジェネレーションを行います。例えば、展示会での名刺交換やWebサイトからの問い合わせなどで連絡先を獲得していきます。
3.リードナーチャリング(見込み顧客育成)
獲得した見込み顧客の中には、商品をすぐに購入したいと考える「今すぐ客」とまだ購入の検討段階にも至っていない「そのうち客」がいます。多くの見込み顧客が「そのうち客」であり、その場合には中長期的に接点を持ち続け、見込み度合いを高めていくリードナーチャリングを行っていきます。
4.リードクオリフィケーション(見込み顧客選定)
リードナーチャリングにより、見込み度合いが高まったと判断できた顧客を選別するのがリードクオリフィケーションです。スコアリングなどにより、ホットリードと判断できた見込み顧客を商談へとつなげていきます。
5.商談・受注
ホットリードとの商談を行い、受注獲得となる重要なステップとなります。これまでのプロセスにおいて把握してきた課題やニーズに合わせた商談を行うことが受注獲得へのポイントとなります。
6.顧客維持
顧客との関係は成約したら終了ではありません。成約後も継続的なサポートにより、顧客満足度を高めていくことが大切です。顧客満足度の向上は、後のアップセルやクロスセルにつながり、最終的なLTVの最大化へと貢献します。
BtoBマーケティングを成功させる戦略立案の方法
BtoBマーケティングを始める前に、まずは戦略の立案から始めましょう。
1.環境分析(3C分析・SWOT分析)
環境分析では、自社を取り巻く業界の内部環境と外部環境を分析することで、今企業が置かれている状況を客観的に把握し、自社が参入できる市場機会を明確にします。
ここで環境分析を行うことで、競合他社との差別化を図り、顧客ニーズをより明確に洗い出すことができるのです。その結果、自社の課題の明確化だけでなく、強みを活かした戦略立案につながります。
ここでは、3C分析とSWOT分析というフレームワークの活用が効果的です。
2.マーケティング戦略の立案(STP分析)
次に、環境分析の結果をもとにしたSTP分析を行い、マーケティング戦略を策定していきます。STP分析では、市場ニーズの細分化、狙うべき市場の絞り込みを経て、その中で自社の立ち位置を明確にしていきます。
3.マーケティング戦略の実行(4P分析)
STP分析を行い自社の立ち位置が明確化したら、実際に商品やサービスをどのように販売していくのか、4P分析を活用して具体的な実行戦略の設計を行います。
策定した戦略は実行に移し、その結果をもとに評価を行います。結果が伴わない場合は、再び戦略の見直しを行います。
BtoBマーケティングで実施したい5つの施策
ここでは、BtoBマーケティングで検討すべき5つの具体的な施策についてご紹介します。
【1】SEO
SEO(Search Engine Optimization)は、直訳すると「検索エンジン最適化」となります。Googleなどの検索エンジンにおいて、できるだけ検索結果の上位に表示されるようにする施策のことを指します。ホームページへの流入数を増やす施策として、もっとも一般的な施策です。既にWebサイトをお持ちの方も多いと思われますが、せっかく作ったものですからたくさんの人にみてもらいましょう。
さまざまな集客施策がありますが、BtoBではまだ検索エンジンが主な流入経路のひとつです。その検索エンジンで検索結果の上位に表示されるかどうかは、流入数に大きく影響するため非常に重要です。
SEOのポイントは大きく以下の2つです。
- ・「検索してきた人にとって有益な情報があるか」
- 検索したユーザーにとって有益な情報があり、その情報が見つけやすいサイトやページは検索の上位に表示される可能性が高いです。
- ・「検索エンジンが理解しやすい作りになっているか」
- せっかく有益な情報を用意しても、検索エンジンがそれを正しく認識できなければ意味がありません。こちらは、Webサイトの中のソースコードの構造を作り替えたりするなど、技術的な作業になる為、外注してしまうのも一つの手段かもしれません。
【2】リスティング広告
ご存知の方も多いかもしれませんが、リスティング広告とは、検索エンジンを使用した時に表示される広告のことです。検索連動型広告とも呼ばれ、予め指定されたキーワードが検索された際に表示される広告のことです。Web広告は近年その種類が増えていますが、まずはリスティング広告から実施してみてはいかがでしょうか。

※リスティング広告イメージ画像
検索エンジンからの集客をおこなう点ではSEOと同じですが、リスティング広告は費用を払えばある程度すぐに検索結果の上位に表示されるので、短期的な流入やお問い合わせの獲得には効果的です。
ただし、広告を出稿している間はずっと費用がかかるという点もあります。逆にSEOは上位表示までに比較的時間がかかる施策ではありますが、一度上位表示ができれば(もちろん順位が下がる可能性もあります)、あまり費用をかけず継続的な流入を確保できます。
【3】Webサイト改善
集客施策をおこなってWebサイトにある程度訪問者が増えてきたら、次はWebサイトの改善もおこないましょう。せっかく費用をかけてWebサイトに来てもらっても、内容を見てもらい、結果として興味やお問い合わせに繋がらなければ意味がありません。内容が判りやすいか、導線は見つけやすいか、少しずつ改善していきましょう。
アクセス解析ツールを用いると、例えば
「トップページにはきてくれたが、製品紹介へのリンクをクリックしてもらえてない。」
「メニューボタンをつけたが全くクリックされていない。」
といったことが分かるようになります。
リンクが目立たないため読者が気づいていないのかもしれませんし、ボタンのデザインが悪くてクリックできるものだと分かりにくいのかもしれません。原因はすぐには分かりませんが、少しずつホームページを変更してみて、またアクセス解析の結果を見て、日々改善をしていきましょう。
アクセス解析ツールは、Google Analyticsを代表として無料のものも充実しています。ただし、設定方法が複雑なものもあるので、分からない場合は有料のサポート付きツールを用いるのもいいかもしれません。また、サイト改善にはA/Bテストも効果的なので、さらなる改善を目指す方は、検討しても良いと思います。
"Webサイト改善が先か集客が先か"という議論もありますが、ある程度の来訪者がいないと、Webサイトのどこを改善すべきかが判らないので、ある程度の来訪者を確保しつつWebサイトを改善するという流れが判りやすいと思います。
【4】外部媒体の活用
Webサイトの集客がある程度できてきたら、次は外部媒体の活用も検討してみてはいかがでしょうか。外部媒体の活用と言っても、記事広告や媒体会員へのターゲティングメールなど、いろいろサービスはありますが、おすすめしたいのは、リード獲得型の外部媒体です。
ホワイトペーパーのダウンロードメディアから見積依頼を獲得できるものまで様々あり、自社でアプローチできない層の見込顧客からのお問い合わせを獲得できるという点もメリットのひとつです。媒体や、自社の商材・サービスによって成果も異なると思いますが、リード獲得を増やしたい場合には検討してみてもよいでしょう。
【5】メール配信
メール配信も、比較的スタートしやすい施策のひとつです。配信先の方の役に立つような情報を定期的に配信することで、信頼関係を育み、将来商談に発展するかもしれません。また、自社セミナーへの集客に用いたり、新しいサービスの紹介などをしてみてもいいかもしれません。配信先の方の興味やニーズに合う内容であれば、成果も出てくるはずです。
BtoBマーケティング成功のポイント
最後に、BtoBマーケティングを成功させるために欠かせない2つのポイントをご紹介します。
関連部門と連携して行う
これまでに解説してきたマーケティングプロセスは、マーケティング部門だけでなく営業部門やカスタマーサクセス部門も関わっています。
部門間での認識の擦り合わせなど、同じ目的を持つことで、適切な施策を行えるようになるため、セールスに関わる全ての部署との連携が重要となります。
ツールの導入で業務効率化
BtoBマーケティングを行うには、見込み顧客情報の管理、確度が高い顧客の抽出、メール配信など多くの工数を必要とします。それらを部門間でスムーズに共有するためにも、MAツールやSFAといったITツールの活用がおすすめです。
しかしツールには多機能なものも多く、自社でつかいこなせなくては意味がありません。まずは自社で行う施策に必要な機能を洗い出し、ツールを選定しましょう。
おわりに
今回は、BtoB企業がマーケティングを始める際に参考にしてほしい、基本的なマーケティング施策を5つご紹介しました。これらの施策だけでも、成果が出るようになるにはかなり労力を要すると思います。しかし、根気よく続ければ必ず集客効果があるはずです。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
また、その他にも「展示会出展」や「セミナー開催」、「ナーチャリング」など、マーケティング施策はたくさんあります。ただ、一気に始めても改善や効果検証が大変になるので、徐々に施策を実施して改善を続けながら、自社にあったマーケティングの在り方を作っていくことをおすすめします。
これを読んでもっとUrumo!
この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。