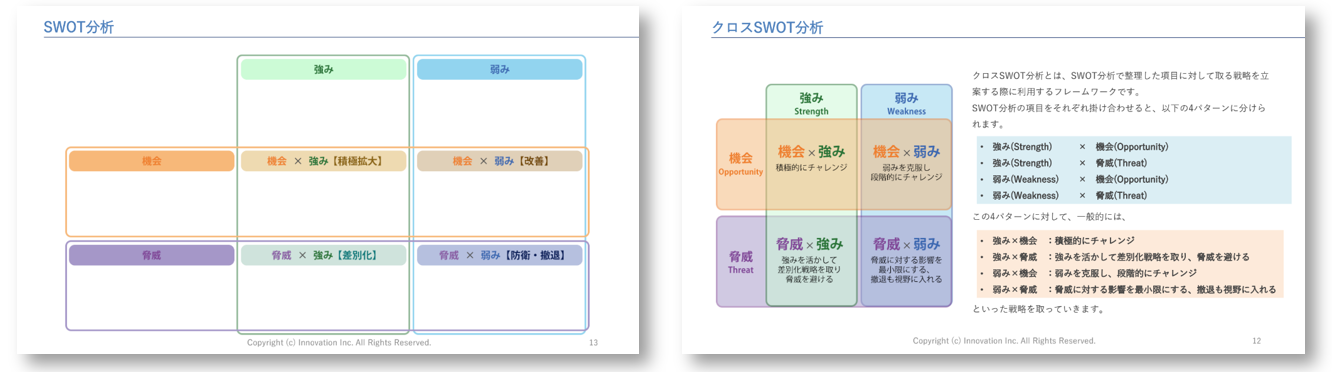「ほうれんそう」とは?業務を円滑に進めるビジネスマナーの基本。

ビジネスマナー用語として古くから使われてきた「ほうれんそう」ですが、現在のビジネスでも多く活用されています。この記事では、基本の「ほうれんそう」とは何か、また「ほうれんそう」の活用の仕方について解説していきます。
「ほうれんそう」とは
「ほうれんそう」とは、「報告」「連絡」「相談」のことです。ここでは、具体的に「ほう」「れん」「そう」それぞれの主な活用場面についてご紹介していきます。
・報告とは
報告とは主に、業務の進捗状況や、結果などを伝えることです。
またトラブルなどが起きた際には、迅速に報告することでその後のフォローや指示を受けることができます。上司から報告を求められる前に、自ら報告をすることが大切です。
・連絡とは
連絡とは主に、業務上の予定や、今後の作業内容などこれから起こることを伝えるときに活用します。
連絡をする際には、要点を絞り、正確な内容を迅速に伝えることが大切です。また、上司から部下だけでなく、社内全体で行う必要があります。
・相談とは
相談とは、問題や課題が発生した際に、意見を求めたり改善策を指示してもらう際に行います。
相談せずに、自己判断で業務を進めたことで失敗につながることも多いため、早めに相談することが大切です。また相談の際には、事前に相談内容をまとめ、内容を明確に伝えることも重要です。
「ほうれんそう」の重要性
ビジネスの現場においては、常に適切な判断を行い、迅速に対応することが求められます。そこで、迅速に情報の共有ができる「ほうれんそう」の活用が重要とされています。
「ほうれんそう」が習慣化されている現場では、タイムリーな情報共有により、トラブルが起こる前や、大きなミスが発生する前に対応することができます。例えば「ほうれんそう」がない環境だった場合には、トラブルの発見の遅れから、大きな損失につながることも考えられます。
「ほうれんそう」による情報共有があれば、早期にトラブルに気づき、ミスを未然に防ぐことができるのです。さらに、業務上の進捗状況を把握するためにも「ほうれんそう」は必要です。
進捗状況を把握できていなければ、業務にタイムラグが生じ、生産性を下げる恐れもあります。進捗状況を「ほうれんそう」できていれば、仕事を進める際に必要な情報が常に把握でき、円滑に業務を進めることができます。
このように迅速な情報の共有によって、損失を未然に防ぎ、業務を円滑に進められることで、チームだけでなく会社全体の生産性を上げることにつながります。このことから「ほうれんそう」の習慣化が重要とされているのです。
「ほうれんそう」の伝え方
ここまで「ほうれんそう」の内容や、重要性についてご紹介しましたが、ここでは実際にどのように伝えたら良いのか、解説していきます。
・明確な内容で伝える
「ほうれんそう」を行うことは重要ですが、全てにおいて指示を求めるのではなく、必要な時に、明確な内容で伝えることが重要です。まずは伝えたい内容を自身がしっかりと把握し、伝える際には、結論から理由の順で話すといいでしょう。
・伝えるタイミング
「ほうれんそう」は状況に応じて、適切なタイミングで行うことが大切です。忙しい上司に対し、進捗の報告を作業を止めてもらってまで伝えるべきなのか、作業が終わってから報告するのか、適切なタイミングを見極めましょう。
反対にミスやトラブルが起きた際など、迅速な報告が必要な場合もあります。そのため、状況や内容に合わせたタイミングで伝えることが重要です。
・伝える手段
「ほうれんそう」の伝え方には、口頭だけでなく、資料を用いた記述という手段もあります。内容が複雑であったり、多くの人に伝える必要のある内容の場合は、記述で伝える方が効率的です。しかし、早急に伝える必要がある場合には口頭で行いましょう。
「ほうれんそう」には、「おひたし」で返す
最近では、部下に対する基本姿勢として「おひたし」を掲げる企業も増えてきています。「おひたし」とは、「怒らない」「否定しない」「助ける」「指示する」のことです。
「ほうれんそう」してきた部下に対して「おひたし」で対応することで、部下との良好な関係構築につながり、業務をより円滑に進めることができるようになります。
また「おひたし」で返してくれる上司には、部下も「ほうれんそう」しやすく、よりチームワークを高めることができ、チームとしての生産性の向上にもつながります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。「ほうれんそう」は円滑な業務を行う上で、重要なコミュニケーションツールです。「ほうれんそう」を習慣化させるためには、「いつでもほうれんそうしやすい環境」作りも大切な要因となります。
個人だけではなく、社内全体で「ほうれんそう」を心がけ、円滑な人間関係を築くことにより効率的に業務を進めていきましょう。