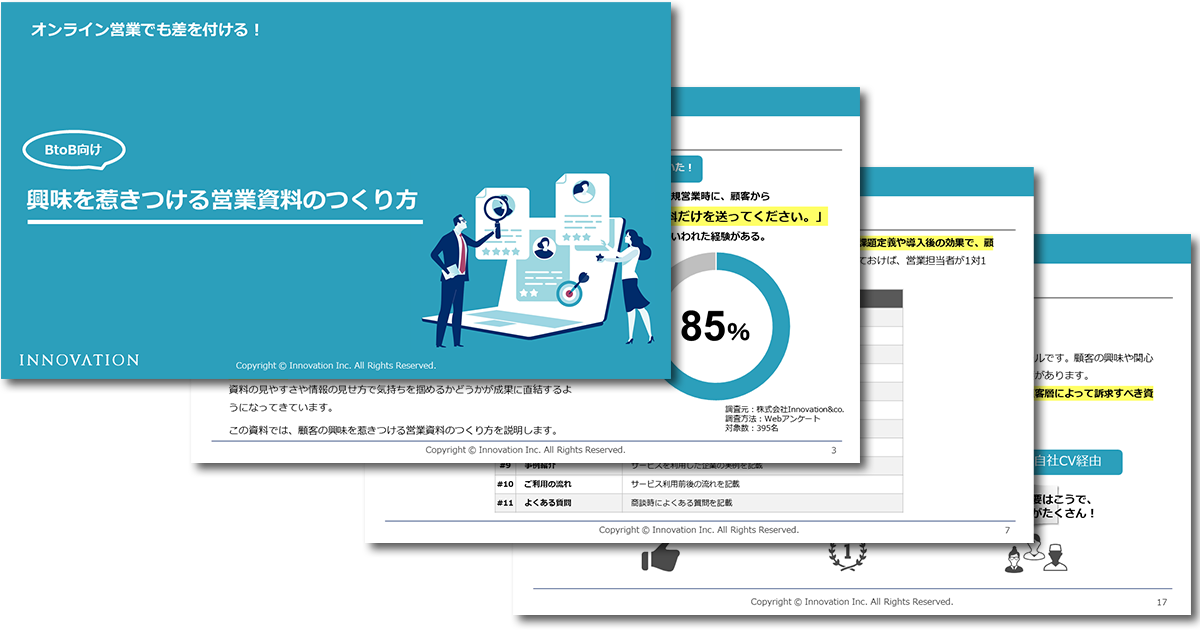成果につながる営業資料の作り方【資料作成手順とポイント】
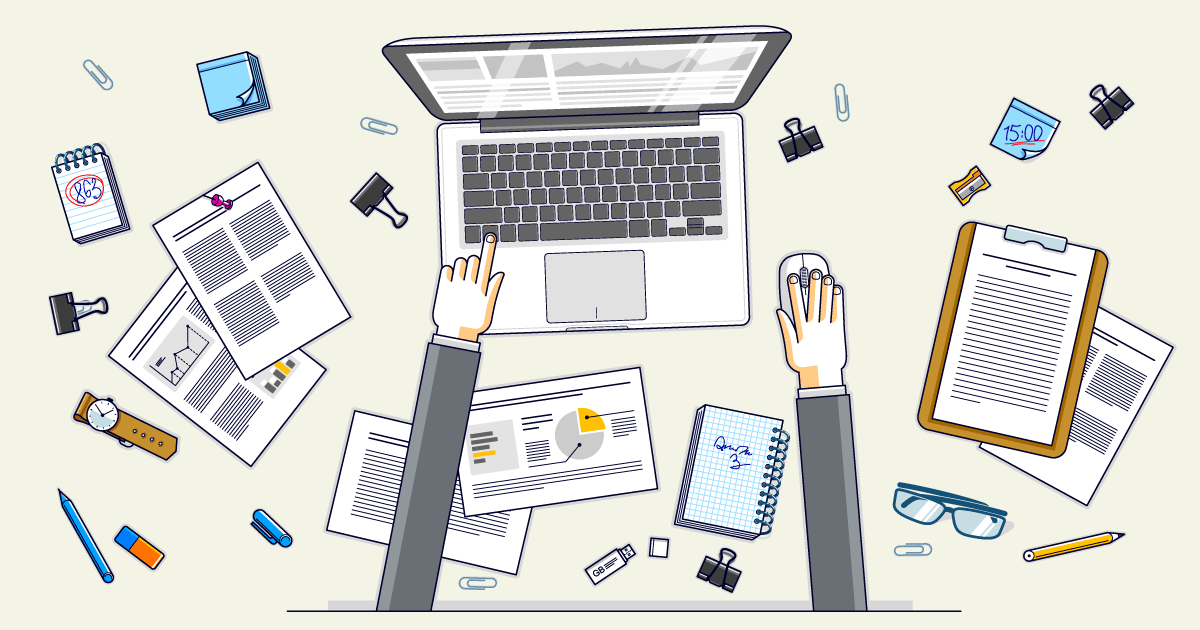
商談の際に、口頭だけでは難しい商品説明も、自社の商品やサービスの情報をまとめた営業資料があることで、より効果的に商談を進めることができます。
また、市場の変化に伴い、オフラインで行う対面営業でなくオンラインでの営業活動を行うことが主流となってきており、これまで以上に営業資料が重要視されるようになりました。
そこでこの記事では、オンライン営業の商談化率や受注率向上につながる営業資料の作り方や、意識しておきたいポイントについて解説していきます。
営業資料が重要とされる理由
オンライン営業は、対面での営業に比べ、営業担当者の顔や表情などを見ていることが少なく、温度感が伝わりづらかったり、コミュニケーションが難しいことが課題とされています。さらに、そこで活用される資料が見にくかったり、どこを話しているのかわかりづらかったりすると商談の成功は難しいでしょう。
このような課題を払拭するためにも、口頭での説明を補完でき、提案がより伝わる営業資料の作成が求められています。
ここでは、営業資料を重要視すべき理由をさらに詳しく見ていきましょう。
属人化の防止や提案内容の標準化につながる
対面営業を行う場合、営業担当者のスキルやノウハウによっても結果は大きく左右されます。そこで提案力のある営業担当者が顧客に伝えていることや、話している内容をコンテンツ化した営業資料を作成することで、提案内容が標準化され、属人化を防ぐことができます。
これにより、営業部門全体で営業の質を高めることができれば、商談化率や受注率向上も期待できます。
社内検討の際も活用される
商談相手である営業先の担当者と、実際に購入の意思決定を行う決裁者が異なることも多く、その場で契約に至らないことも少なくありません。
そうした場合に、営業資料が手元に残ることで、その後の社内検討の際にも活用してもらうことができ、営業担当者がその場にいなくても、商談化や受注へとつなげることができるのです。
営業資料作成前の準備
まずは、資料作成に入る前に確認しておきたいポイントについて解説します。
1.ターゲットを想定する
営業資料は営業先の担当者だけでなく、決済者などさまざまな人の目に触れることを想定して作成する必要があります。
誰が見ても理解しやすく、社内検討の際にも活用してもらえる構成や内容で作成することを意識しておきましょう。
2.AIDMAモデルを活用し利用シーンを想定する
営業資料を作る際は、利用されるシーンを想定する必要があります。そこで活用できるのがマーケティングフレームワークの1つであるAIDMAです。
AIDMAとは、
- ・Attention(注意)
- ・Interest(関心)
- ・Desire(欲求)
- ・Memory(記憶)
- ・Action(行動)
の5つの頭文字を取ったもので、顧客が購入に至るまでの興味関心度合いをフェーズごとに当てはめ、見極めを行います。顧客の興味関心がどのフェーズにあるかを理解することで、フェーズに合わせた営業資料を作成することができます。
例えば、フェーズが「A・I 」の場合、まずは自社を知ってもらうためにも、資料パンフレットなど簡潔で目を惹きやすいものがいいでしょう。
またフェーズが「D」の顧客には、提案資料などといった商品について理解してもらえる資料を作成します。顧客に製品やサービスについて理解してもらうため、わかりやすい資料を作ることが大切です。
さらに「M」の場合は、個別提案書など、顧客のニーズに寄り添った内容で購買につながる資料を作成します。ここでは担当者だけでなく決済者が目を通すことを想定し、明確なメリットを明示することも重要となります。
3.利用シーンに合わせた構成とデザインを考える
使用されるシーンやシチュエーションによっても資料の構成を変える必要があります。例えばパンフレットの場合、自社を認知してもらうための資料なので、文字ばかりの資料ではなく写真や図版を活用したほうが読む人にわかりやすく興味をもってもらえるでしょう。 また利用させるシーンがオンラインの場合には、文字サイズを大きくするなどの配慮も必要となります。
このようにシチュエーションに合わせ、顧客が読みやすい資料作りを心がけることが重要となるのです。
営業資料の作り方
営業資料作成の際、顧客が読み進めたいと思う構成にすることが重要です。サービス説明や機能説明のみの資料ではなく、課題定義や導入後の効果を明示するなど、顧客ニーズに対しての提供価値が伝わる資料にしましょう。
ここでは一般的な構成例をもとに、営業資料を作成する際に押さえておきたいポイントについてご紹介します。
- 一般的な構成例
- 表紙
- 商品・サービス紹介
- よくある課題
- 導入することで得られる効果
- 選ばれる理由
- 導入事例
- 料金
- 導入手順
- よくある質問
- 会社概要
- 問い合わせ先
1.表紙・タイトル
営業資料の表紙やタイトルは、企業やサービスの第一印象を左右する重要な役割を持ちます。タイトルでは、どのような商品やサービスなのか概要がわかる様に一言で簡潔に紹介しましょう。
また簡潔に要点を伝えるためには、キャッチコピーの活用も効果的です。顧客にとってのメリットを明示することで、資料を読みたいと思ってもらうことが大切です。
- POINT
- ・資料の概要がわかるタイトル設定
- ・自社サイトに合わせた表紙デザインにする
2.商品・サービス紹介
次に、商品・サービスの概要を具体的に解説していきます。
ここで重要なことは、顧客にとって使用する価値のある商品であることを伝えることです。使用することで得られる効果やメリット、さらに他社と比べたときの強みなどを明示しましょう。
- POINT
- ・リード文でサービス概要がわかるようにする
- ・商品画像のキャプチャを添付する
- ・箇条書きでメリットを記載する
3.よくある課題
顧客の抱える課題や問題点を具体的に提示することで、購入の動機づけを行います。また、課題が顕在化していない顧客でも、よくある課題を提示することで潜在的な課題に気づくこともあるでしょう。
顧客が自社に置き換えて商品やサービスの使用を想定できるよう、状況や課題を具体的に提示することがポイントです。
- POINT
- ・サービスの導入で解決できる課題を提示する
- ・ターゲットに合わせて想定できる課題を提示する
4.導入することで得られる効果
ここでは自社のサービスを導入することで得られる効果、つまり解決策の提示を行います。課題の提示により顧客が課題を認識したら、自社製品を使用することでその課題を解決できることを提示しましょう。これにより、購入意欲の向上につながります。
- POINT
- ・サービスの導入によってどのように解決できるのか具体的に提示する
- ・ROI(費用対効果)も提示する
5.選ばれる理由
自社の商品やサービスが選ばれている理由についても明示しておきましょう。既存顧客や見込み顧客へのヒアリングをもとに選ばれる理由について分析しましょう。また、このときターゲット企業と近い業種のヒアリング結果をもとにするとより、商談相手にとって効果的な営業資料にすることができます。
- POINT
- ・競合他社にはない自社の強みを記載
- ・これまでの自社商品の受注理由から選ばれている理由を記載
6.事例紹介
顧客にとって魅力的なサービスだとわかっても、実際にそのような効果が得られるかどうか信頼されなければ購買にはつながりません。 そこで導入事例や実績の紹介で訴求ポイントの理由付けを行いましょう。
そうすることでより相手に安心感を与えられ、信頼の獲得にも繋がります。また、顧客と事業領域の近い事例を紹介することでより主体性を持たせることができるでしょう。
- POINT
- ・ターゲット企業と事業領域の近い事例を記載する
- ・導入企業の声として記載する
- ・効果はわかりやすく数字で記載する
7.料金
次に、商品・サービスの利用料金を提示します。顧客が社内での稟議を通す際にも、明確に価格を提示しておくことが大切です。商品の価値に合う価格であることを踏まえ、きちんと説明しましょう。
また複数のプランがある場合には、高価格プラン・中価格プラン・低価格プランといった料金表を記載することで、金銭的な抵抗感を払拭し、予算に合わせた商品を選定しやすくなるでしょう。
- POINT
- ・複数のプランがある場合には、表を活用する
- ・利用料金以外のオプション料金があれば記載しておく
- ・支払方法を記載する
8.導入手順
お問い合わせが来てから料金が発生するタイミングや作業工程といったサービス導入までの手順をわかりやすく記載します。一目で流れがわかるような表にしたり、顧客が次にどのようなアクションをしたらいいのか、契約までの流れを想像しやすいようにしておくことが大切です。
- POINT
- ・表などを使って一目で導入までの流れがわかるようにする
- ・料金が発生するタイミングを明記しておく
9.よくある質問
営業資料には、よくある質問についても記載しておきましょう。ここでは、商談時によく聞かれることをベースに記載します。
またこのとき、もともと自社サイトなどに載せているFAQなどは問い合わせ前の質問への回答であるため営業資料に載せるよくある質問とはシーンが異なります。
- POINT
- ・商談時によく聞かれる質問を記載する
- ・LPのFAQとは内容が異なる場合が多い
- ・ネガティブな質問には表現を工夫して掲載する
- ・よくある質問は都度更新していく
10.会社概要
自社がどのような企業なのか、信頼性の獲得のためにも、概要についてもしっかりと記載しておきましょう。
- POINT
- ・会社名・住所・電話番号・代表者名・事業内容など
- ・従業員数や拠点数、資本金、上場有無など信頼性の獲得につながる情報
11.問い合わせ先
営業資料を読んでもらい、顧客の購買意欲が高まったのにも関わらず、商品を購入するための連絡先やコンタクト方法が書かれていなければ購買には至りません。
そこで営業資料の最後には、問い合わせ先など、顧客が次のアクションを起こせる連絡先の明示を忘れずに行いましょう。
- POINT
- ・次のアクションを提示する
- ・メールアドレスやURLだけでなく電話番号やFAX番号が求められることもある
押さえておきたいデザインのポイント
営業資料を作る際は、読み手がわかりやすい資料づくりを心がけましょう。ここでは、営業資料をより読みやすいものにするためのデザインのポイントについてご紹介します。
1ページの内容は、1メッセージに絞る
営業資料作成の際は、1ページの内容を1つのメッセージに絞っておきましょう。
1ページにたくさんの情報を詰め込みすぎると、本当に伝えたいことがわかりづらくなってしまいます。グラフや図表も活用し、テキストばかりの内容とならないようにすることで、読みやすい営業資料になります。
オンライン上でも見やすいフォントの設定
営業資料では見やすいフォントを使うことも大切です。特にオンライン上で営業資料を活用する場合は文字サイズを大きくするなどの配慮も必要です。
- ・使用するフォントは1種類のみにする
- ・文字サイズはタイトルや見出しごとに分ける
- ・行間を揃える
などを意識すると資料全体の統一感を出すことができます。また自社サイトと、ある程度デザインを揃えるなどすると資料を作りやすくなるでしょう。
ビジュアルメインで文字数は減らす
営業資料では、たくさんの情報を詰め込みすぎると伝えたいことがわかりづらくなってしまいます。視認性を確保するためにも、文字数は多すぎないようにし、グラフや図表、イラストを活用し、見やすいページを作成しましょう。
使用するカラーは3色までにする
多くの色を使いカラフルすぎる資料は読み手に煩雑な印象を与え、伝えたい部分がわからづらくなることがあります。そこで使用するカラーはメインカラー、アクセントカラー、文字カラーの3色に絞りましょう。
このとき、メインカラーは自社サイトのイメージと合わせて選ぶとより統一感を持たせることができます。
また、過度な装飾も重要な部分がわからなくなってしまうこともあるため、不要な装飾が多くならないようにすることも大切です。
数字でインパクトを与える
数字を入れることで、内容に具体性を持たせ、インパクトを与えることができます。たとえば「生産性30%向上」や「10万円のコスト削減」といったように、具体的な数字で伝えることで説得力が増します。
また、反対に数字を使わない抽象的な表現は、顧客との認識の相違にもつながり兼ねません。顧客との齟齬をなくすためにも、数字で具体性を持たせましょう。
営業資料作成時に意識しておきたい注意点
最後に、営業資料を作るうえで気を付けておくべき点についても見ていきましょう。
読み手に寄り添った資料にする
自社が販売したいサービスの売り込みをするだけの資料ではなく、顧客の悩みや課題に寄り添った資料作成を意識しておくことが大切です。
解決の手助けとなるサービスを紹介をすることで、顧客の興味を引く可能性が高まります。また資料内で顧客が抱くであろう不安や、疑問についても先回りして予測し、記載しておくことが信頼性を図ることにもつながります。
顧客に合わせて複数の資料を作成する
営業資料は、顧客の興味喚起のためのツールです。営業資料は1種類だけでなく顧客の興味や関心に合わせて、資料の内容を変えるなど複数作成しておく必要があります。閲覧率の高い資料活用を増やすことで、見込み顧客の資料閲覧率が高まり、結果、商談獲得数の向上につながるのです。
また、複数作成した資料それぞれの閲覧率を確認しましょう。閲覧率の高いものはメイン資料に活用し、閲覧率の低いものは資料の見直しを行います。
商談後の活用も考慮して作成する
商談時に決裁者が同席していなくても、資料は決裁者にアピールできる貴重なチャネルです。営業担当者が商談時に担当者に上手に伝えられても、その担当者が社内に同じ質で展開できるとは限りません。
口頭で説明した内容は残りませんが、資料は残ります。資料が決裁者の手に渡る機会は十分にあります。資料の内容や体裁を見て、企業やサービスへの信用を判断する人が一定数存在するため、それを踏まえた資料を作成することが必要です。
定期的なブラッシュアップも忘れない
市場や競合を含め、世の中の変化スピードは上がっているため、定期的に資料を見直す必要があります。そこで、常に最新の情報となるよう最低でも四半期に一度は営業資料の見直しを行うようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。営業資料を作る際は、まず誰のための資料なのかしっかりと見極めたうえで作成に取り組むことが大切です。作成前にターゲットを明確にしておくことで、課題や不安を把握し、顧客に寄り添った内容の営業資料を作ることができます。
また自社の製品やサービスを売り込むのではなく、あくまで顧客のメリットを明示した営業資料を作成することが、自社の成果へとつながっていくでしょう。