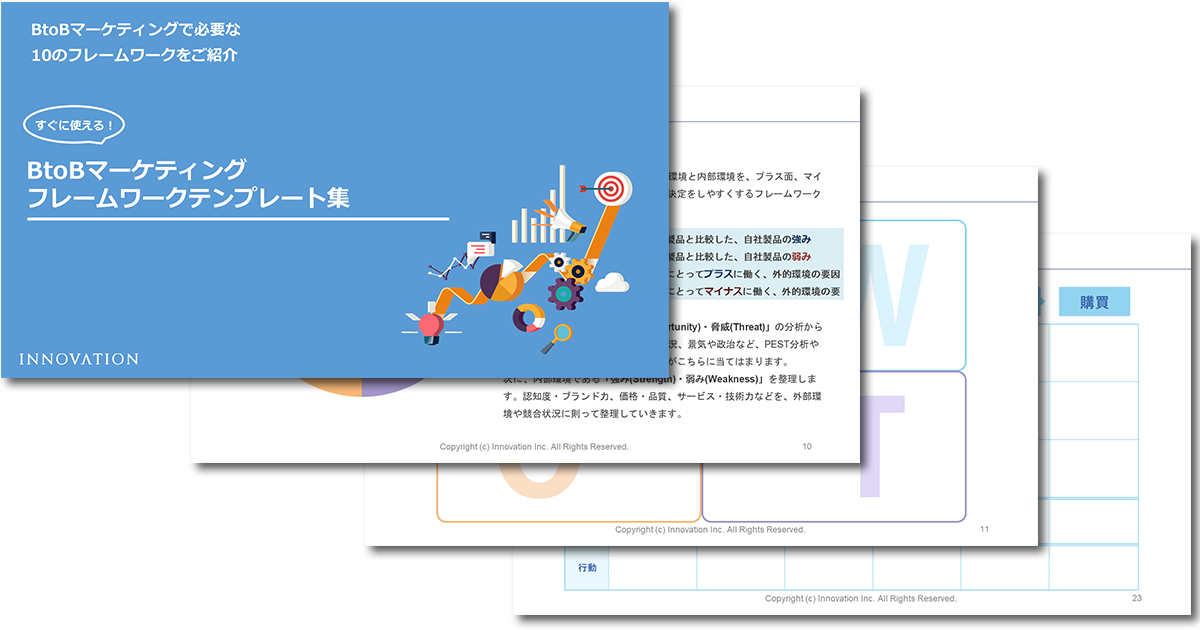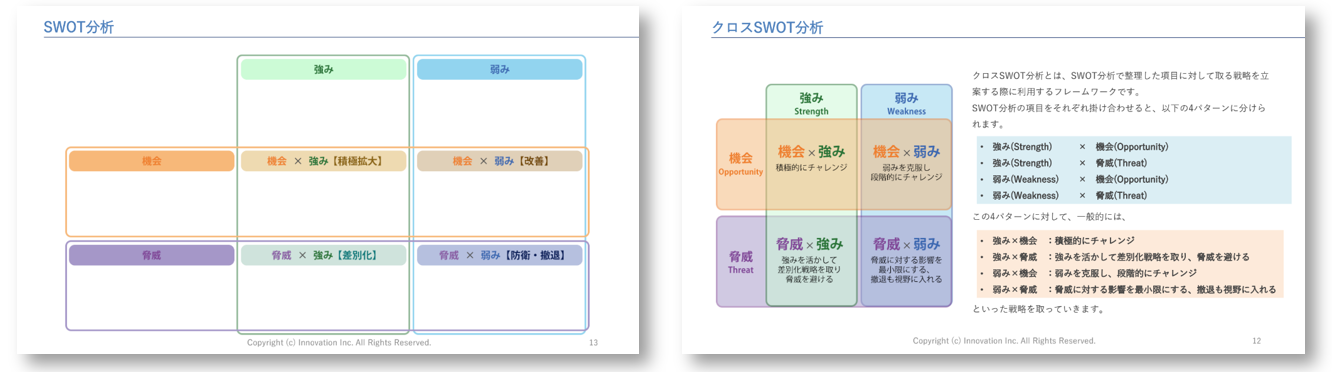効果的な情報収集のポイント7選。情報の渦に飲み込まれないための秘訣

みなさん、普段の情報収集はどうやっていますか?「調べてたらもうこんな時間!まずい!」といった経験は誰しもがあると思います。デキるビジネスパーソンは、必要な情報を瞬時に持ってくるイメージがありますが、どうやっているのでしょうか?
今回は情報収集における前提や、してはいけない、こうあるべきといった心構えを紹介していきたいと思います。
情報収集における前提・目的
はじめに、忘れがちな情報収集の前提と目的を整理していきます。
前提:情報収集の目的は「アウトプットと成果」
自戒も込めて書きました。まずは情報の前提から確認していきましょう。
情報とは、「なにかをするための根拠や、説得力を増すためのもの」だと思っています。「情報を集めること」自体が目的ではありません。
つまり、情報収集とは、「前に進むための情報を集めること」が目的です。この前提と目的を忘れないようにしましょう。
例えば、今後の市場動向についてプレゼンするとします。その場合、現在の市場動向と、将来予測の情報を調べる必要があります。「今後のIT市場は伸びていく」だけだと、信憑性がありません。市場規模はこれくらいあり、A社の調査の結果、市場成長度はこれくらい...といった主張ができれば説得力が増しますよね。
ただ、現在の市場動向と将来予測の情報が必要だ、という考えもなしに無闇に調べると、時間がいくらあっても足りません。ですので、必要な情報に当たりをつけ、少ない時間で調査をしましょう。
情報収集は、こういった前提と目的があったうえでするべきです。収集家にならないように注意しましょう。
「仕事」と「趣味」を切り分ける
情報収集をしていると、途中から「趣味」になってしまっているときがあります。これは、興味がある分野の調査中や、遭遇した情報が面白かった際に陥りやすい現象です。
会社の「仕事」を、時間内で最大限の成果を生む行為と捉えた場合、向かうべき対象は仕事、もしくは会社です。「趣味」の対象は自分に向いてしまっています。
能力の向上や知識の深掘りはいいことですが、あとで個人的に調べるなど、目的に沿った情報収集をしましょう。まず向かうべき先は「仕事」です。
もちろん、深堀りすれば質があがる...というものはまだまだ調べたほうが良いですね。しかし、仕事には期日があるものも多いハズ。「仕事」と「趣味」を混同しないように気をつけましょう。
情報収集における成果とは?
では、「情報収集における成果」とはなんでしょうか。それは、
- ・仕事を前に進める情報を、可能な限り早く手に入れること
- ・いい意味で、目の前の仕事の幅を広げること
だと思います。
仕事では、まず時間が決まっており、高いクオリティも求められます。当たり前ですが、少ない時間で高いパフォーマンスを発揮すると、評価が高くなりますよね。情報収集は、そういったパフォーマンスをあげるための手段です。少ない時間で高いパフォーマンスを発揮できるよう、情報収集していきましょう。
情報収集時に「してはいけないこと」
情報収集の前提は伝わりましたでしょうか?次に、情報収集を有効に進めるうえで「してはいけないこと」から見ていきましょう。
・時間を決めずにやること
「してはいけないこと」ひとつ目は、「時間を決めずにやること」です。会社や人にもよりますが、多くの場合1日の勤務時間は7〜8時間です。時間を決めずに「気づいたら時間がたってた!」となるのと、30分と決めて「ここまでは見えたから、あとはこの部分の情報収集を追加で行おう」とある程度成果をだすのでは、どちらがいいかは自明ですね。
・情報源をきちんと確認しないこと
あやふやな情報は信憑性がありません。特にビジネスの世界においては、根拠が必須です。行政やリサーチ会社の情報は信頼度が高いので、有効に活用していきましょう。
・必要ではない情報や網羅的に調べること
いかに早く情報源にたどり着き、それを獲得するかが重要です。網羅的に調べると、時間のロスが生じてしまいますので、未知の情報を調べる際にも、仮説を立てて調べましょう。
情報収集時に「するべきこと」7選
「してはいけないこと」を見てきましたが、次に「するべきこと」を7つ紹介します。
1. 「成果は何か」明確にしてから調べる、アウトプットを意識する
作業に取り掛かる前に、今回の情報収集における成果を一旦決めましょう。調べている際は、「アウトプット時にはどうするか?」と念頭に置いて調べてましょう。情報収集をしていると、情報量に埋もれてしまうときもあるので、紙に書いておいても有用です。
2. 時間を決めて調べる
15分、30分と決めて調べましょう。
例えば、提案書を作る場合、まず、何時間で作るのか計算します。次に、構成を考えた上で、「各パートはこれくらいの時間をかける」と計算します。そして、「調べなければわからない分野はこれくらいあり、何分かける」と決めます。そのように計算した結果、情報収集に15分必要ならば、計画に説得力が生まれます。
計算を踏まえた計画ならば、もし仮に15分をオーバーしても、上司にきちんと報告ができ、次の課題が見つかります。自己管理力を向上させるためにも、時間設定をする癖をつけましょう。
3. 情報源にあたり、正確な情報かを確認する
経産省や総務省のデータ、企業独自の調査情報に行き着ければ、よりベターだと思います。情報源がわからないと説得力が失われてしまいます。情報源のURLや参照をメモしておくことが重要です。
4. 調べる前に仮説を持ってから調べる(確認するイメージ)
仮説を持って情報収集に取り掛かり、答え合わせするような情報収集ができれば、自分の考える力を養うこともできます。
また、調べる内容を構造的に整理することが重要です。構造的にAとBは関連している、CはDを深掘ったものだ、などのように、整理して取り掛かると効率的だと思います。
5. 調査した項目を構造的に捉える
調査した項目を構造的に捉えると、トピックが抽象的であるときに有用です。
例えば、Webマーケティングについて調べていた場合を考えてみましょう。コンテンツマーケティングや、オウンドメディアマーケティングも含んでおり、別途調べる必要が出てきたとします。その場合は、抽象的な仮説だったという裏返しなので、別途時間を取って深掘りしていきましょう。
6. オンラインとオフラインを使い分ける
ここでは、オフラインは本、新聞、人、オンラインはインターネットを介在したもの、と定義します。インターネットは誰もが知りうる情報に対して、人からの情報は独自の価値がある可能性が高いです。
一般論と独自の情報を織り交ぜ、オリジナルの意見、主張を持つと情報の価値が増します。
7. why?(なぜ?)so what?(だからなに?)を意識してインプットする
この意識を持つと、インプットの質がひとつ高まります。why?でより情報の深さが増し、so what?で情報が新しいものに生まれ変わります。
例えば、「A社が株を上方修正した」という例で上の考え方をしてみましょう。
- why?を考えると、
- ・既存のBという事業が計画よりもよかった
- ・コストが計画よりもかからなかった
という見方をすることもできます。
- so what?を考えると、
- ・事業により投資をしていくかもしれない
- ・継続的に高い収益を出していくために、社内の管理システムに投資をするかもしれない
という見方をすることもできます。
インプットを最大化するためにも、why?とso what?を意識して情報収集しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
ブログの普及やメディアの多様化から、情報収集の機会は増えてきました。ですが、「興味がある情報のみ追うと教養がなくなる」という懸念も生まれ始めています。
オフラインとオンラインを使い分けたり、サービスによって目的を変えてみると、偏りがなくなり、質のいいインプットができるかもしれません。本記事を活用し、情報収集を有意義に進めていただけたら幸いです。